
こんにちは、ダンナです。
先日、子どもの発達について学びたいという話をしたら、臨床心理士・公認心理師の先生から「ピアジェの認知発達理論がオススメですよ!」と教えてもらいました。→
ピアジェの認知発達理論について簡単に触れ、その理論を基に「0~2歳児のパパ・ママ」の悩みの共有・解決が出来ればいいな~と思い、まとめてみました。
難しいことは抜きにして、やさしく書いています!
※ミルク代やおむつ代のためにアフィリエイトリンクを貼っています。入用でしたらで構いません。当サイトのリンクからご購入いただけますと幸いです。この記事を更新するやる気と原動力になります。何卒よろしくお願いいたします。
はじめに|「正しく育ってるのかな?」と感じたあなたへ
泣いてばかり、舐めてばかり、なんでも口に入れちゃう…
初めての子育て、わからないことだらけで不安になりますよね。
「この子、ちゃんと成長してるのかな?」
「毎日泣いてばかりで心配…」
「なんで何でも口に入れちゃうの?」
そんな疑問や戸惑い、あなただけじゃありません。
でも実は、それ全部「成長している証拠」とのこと…。親の不安は成長の過程と言うことか…?
それ、ぜんぶ「ちゃんと育っている証拠」です
赤ちゃんは、世界に出てきてまだ数ヶ月。目に映るもの、耳に入る音、触れるもの、すべてが初体験。
だからこそ、泣くのも、舐めるのも、全部が学び。そんな赤ちゃんの成長をやさしく見守るヒントとして「ピアジェの発達理論」をご紹介します。
ピアジェの認知発達理論ってなに?ほんの少しだけ知っておこう
難しい話はいりません!必要なポイントだけご紹介
「ピアジェ」とは、スイスの心理学者で、子どもがどんなふうに「考える力」を育てていくのかを研究した人です。
彼は、子どもの成長には「段階」があると考えました。
発達には「順番」がある。それがこの理論の考え方
大人のように考えられるようになるには、ステップを一段ずつ登る必要があります。
いきなり論理的になることはできません。
だから、今のお子さんの「不思議な行動」は、その“登る途中”の自然な姿ということになります。
ニンゲンってすごいよなぁ…
0〜2歳の「感覚運動期」とは?
赤ちゃんは「見て・触って・なめて」世界を学んでる
ピアジェ理論でいう「感覚運動期」は、生まれてから約2歳までの時期のことを指します。
この時期の赤ちゃんは、目で見たり、耳で聞いたり、手で触ったり、なんでも口に入れたりして、五感をフル活用して学んでいます。
頭ではなく、体を使って成長中!
たとえば、大人が本を読むことで新しい知識を得るのに対して、赤ちゃんは“触って確かめる”ことで学んでいます。
だから「なんでも舐める」のは、頭じゃなくて身体で「これはどんなもの?」と学んでいるサインらしいです。
大人も怖いもの見たさに変なフレーバーのお菓子とか食べるもんね!(話が違うか)
「いないいないばあ」は最高の脳トレ
「対象の永続性」ってなに?
「いないいないばあ!」に赤ちゃんがケラケラ笑うのは、ただ面白いだけではありません。
これは「目の前から見えなくなった人や物が、消えたわけじゃない」と理解する大切な学びなのです。
この考え方を「対象の永続性」といいます。
遊びの中で学んでるってすごい!
繰り返し「いないいないばあ」をすると、赤ちゃんの中で「ママが見えなくなっても、また戻ってくる」と理解が深まります。
だから、遊びは学び。毎日のふれあいの中で、赤ちゃんの脳はぐんぐん育っています。
「目の前で消えたおもちゃ」を探さないのはなぜ?
それはまだ“成長途中”なだけ!
たとえば、赤ちゃんが遊んでいたおもちゃをママが隠しても、赤ちゃんが探さないことがあります。
それは「対象の永続性」がまだ身についていないから。
でも安心してください、それは当たり前のこと。2歳近くになってくると、自然と探すようになります。
できるようになるタイミングは子どもそれぞれ
赤ちゃんによって、その“気づき”のタイミングは違うようです。当然っちゃ当然か。
周りの子と比べずに、「この子なりのスピード」を信じてあげましょう。
そうは言うものの気になるよね…
よくある育児の悩みと、ピアジェ的アドバイス
「なんでも口に入れちゃう」→それ、学びのプロセスです
大人にはちょっと困ってしまう行動。でも赤ちゃんにとっては“調べている”真っ最中。
危なくないものであれば、「学んでるんだな〜」と見守ってあげましょう。
「ずっと同じ遊びしかしない」→それは繰り返して理解してる証拠
何度も同じボタンを押したり、ブロックを投げたりするのは「こうしたら、こうなる」と確認している証拠。
繰り返しこそ、理解の積み重ね中らしいですよ!
ティッシュを全部引っこ抜くのも学習中なのか!泣
「急に泣く」→五感で感じた世界にびっくりしただけかも
知らない音、大きな声、冷たい手触り…。大人には気にならないことも、赤ちゃんにとってはドキッとする体験。
泣くのは自然な反応らしいです。
あまり心配しなくてもいい…ってこと!?
親ができること|不安を減らす3つの関わり方
いっしょに遊ぶ
赤ちゃんは「遊び」が一番の学び。
ママやパパと目を合わせながら遊ぶと、赤ちゃんは「安心」と「発見」の両方を感じられます。
口に入れても安全な環境づくり
なんでも触る・なめるのが前提なら、それを前向きに考えて、安心して探検できる環境を整えることが大切です。
怒る前に、ちょっとだけ“観察”してみる
「なんでこんなことを?」と思ったら、少しだけ立ち止まってみてください。
きっとその行動の中に、赤ちゃんの“小さな研究”が隠れています。
子どもの「成長スピード」は一人ひとり違う
比べなくていい、ママ・パパの気持ちを軽くしよう
SNSや育児本には「○ヶ月で○○できる」がたくさん書いてあります。
でも、お子さんは世界に1人の存在。
焦らなくて大丈夫です。笑顔でいる時間が、なによりの栄養です。
うちのエケチェンは世界一かわいいよ
全部わからなくていい。大切なのは“信じて待つ”こと
「理論を全部覚える必要はありません」
ただひとつ、「赤ちゃんは今、必死に世界を学んでいる」
そう思って、少しだけゆっくり構えてみてください。
まあ、僕の子だからね!どうにかなるよ
とはいえ、気になるよ!と言う人は相談を!



そうは言っても気になるものは気になるし…
そんな時は「臨床心理士」へ相談を!
臨床心理士さんは子供の発達における様々な悩みや課題に対して、心理的な面から支援を行ってくれる専門家です。頼れる存在。何だかんだで我が家もお世話になっています。
どうしても気になる!という方は、一人で抱え込まずに専門家に相談してしまう方が良いでしょう!親の精神状態も大切だからね…。
以下のブログとかは発達心理について簡単に解説しているので、個人的にススメです。
まとめ|「今日もよく泣いたね」が、ちゃんと育ってる証拠
心配になったら、この記事に戻ってきてください
ピアジェの理論は、赤ちゃんの“変わった行動”を“意味のある学び”に変えてくれるレンズです。
今日もたくさん泣いて、たくさん触って、たくさん失敗して。
それが赤ちゃんにとっての勉強とのこと。不安だけどね!
どうか、不安を抱えすぎず、一歩一歩、赤ちゃんと一緒に成長していきましょう。
頑張りながらも楽しむぞ!
詳しく学びたい方は以下の書籍がオススメです。
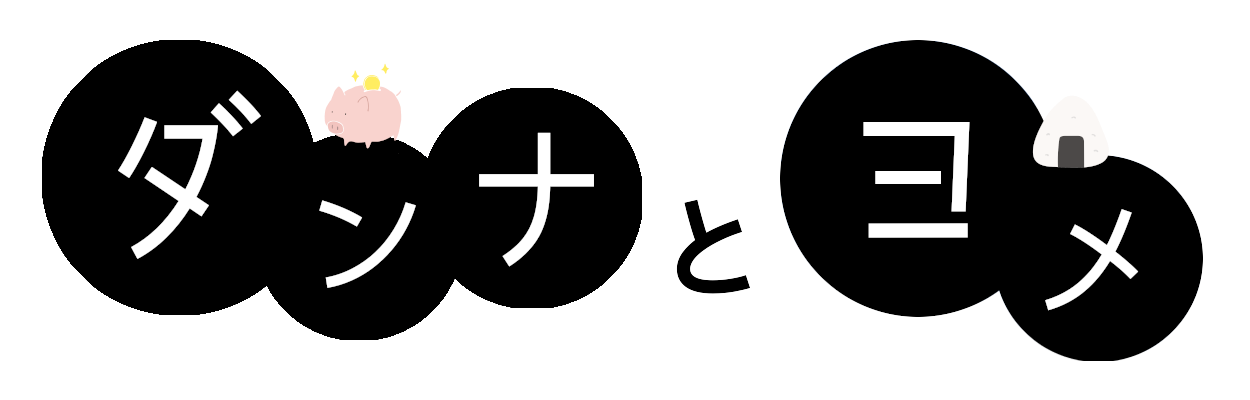

コメント