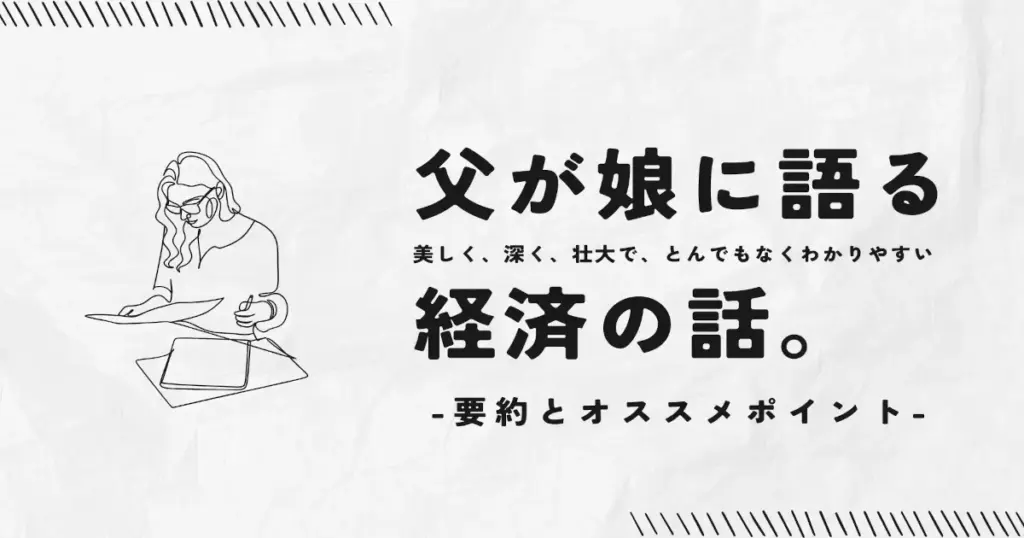
こんにちは、ダンナです。
子を授かり、絶賛育児に奮闘中な僕ですが、趣味の読書だけは睡眠時間を削りながら楽しんでいます。とはいえ、睡眠が3時間おきって大変ですね…。
どうせ読むなら子どもと学べたり、子どもに読ませたい(贈りたい)書籍を探そうか…という思考になり、その一冊目としてオススメできそうな書籍がありましたので共有します。
本書の対象は中学生くらいかな~なんて思います。個人的には小学6年生くらいでも行ける気がする(というか、ダンナは読んでいたレベル)と思っているので、実際に手にとる前の参考として当ブログを読んでいただけると嬉しいです。
※当ブログではアフィリエイトリンクを貼っています。必ず赤ちゃんのおむつ代・ミルク代としますので、当記事が「勉強になった!」「参考になった!」と思っていただけたら、当リンクからご購入いただけると嬉しいです。
『父が娘に語る経済の話。』書籍詳細&基本情報【ヤニス・バルファキス】
基本データ【書籍名・著者・発行日・価格】
- 書籍名:「父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。」
- 著者:ヤニス・バルファキス 著/関 美和 訳
- 発行年月:2019年03月
- 価格:1650円(本体1500円+税10%)
- 出版社:ダイヤモンド社
十代の娘の「なぜ、世の中にはこんなに格差があるの?」というシンプルな質問をきっかけに、元ギリシャ財務大臣の父が経済の仕組みを語る。「宗教」や「文学」「SF映画」など多彩な切り口で、1万年以上の歴史を一気に見通し、「農業の発明」や「産業革命」から「仮想通貨」「AI革命」までその本質を鮮やかに説く。(ダイヤモンド社より引用)
著者について【ヤニス・バルファキス】
ヤニス・バルファキス氏は、ギリシャ出身の経済学者であり、政治家としても活躍しました。
アテネ生まれで、エセックス大学やバーミンガム大学で学び、Ph.D.を取得した後、アテネ大学やテキサス大学オースティン校などで経済学を教えました。専門はゲーム理論や政治経済学で、2008年のサブプライムローン危機を予測したことでも知られています。
そんな彼は本書で、次世代に向けたマネーリテラシーの重要性を強調しています。具体例と親しみやすい語り口によって難解な経済概念を解きほぐし、家族間のコミュニケーションを促進する独自の経済観を提示しています。
著者の経歴がちゃんとしている!というのは、本を選ぶうえで重要な要素のひとつだと思うのです…!
本書の特徴【経済入門・親子で学ぶ】
本書の特徴は「経済学の基礎を専門用語をあまり使わず、娘に語るような対話形式で解説している」という点です。
宗教や文学など、親しみやすい話題を切り口として、大人でも難解な経済学を優しく丁寧に解説されています。いままで多くの書籍を読んできましたが、詳しく難しい内容を話していながら、ここまで優しく噛み砕いて解説している書籍は初めてです。とにかく読みやすかった。経済学の入門として大人にもオススメです。
本書の要約~経済~
経済の始まり:なぜ、こんなに「格差」があるのか?
本書ではまず、経済の起源から触れています。経済の起源は1万年以上前にさかのぼり、農業革命によって余剰が生まれ、それが人々の間で不均等に分配されることで格差が発生しました。これはどの国の歴史を読み解いても同じ現象が起きています。
本書では、「なぜアフリカから強国が出てこなかったのか?」という問いや、地域内で金持ちが簡単に富を築ける仕組みなど、歴史的・地理的視点から格差問題を解説しています。この部分だけでも読む価値がある内容の濃さです。
市場社会の誕生:いくらで売れるか、それがすべて
何気なくつかっている通貨。モノには必ず値段がついています。市場社会(資本主義)は、生産物や労働力などあらゆるものを価格で評価する仕組みというように解説しています。
本書では、「ふたつの価値」(使用価値と交換価値)や、経済学者がすべてを値段で測る考え方について触れることで、より深いところまで解説しています。また、「世界はカネで回っている?」という問いを通じて、資本主義社会の本質にも迫ります。資本主義について子どもにも分かりやすく説明できる!という人は少ないのではないでしょうか。
借金と利益:すべての富が借金から生まれる世界
借金は全て悪いことと思っている人がまだ多い日本において目から鱗の章です。すべての富は借金から生まれているということを御存じでしょうか。借金は経済成長を促進するエンジンであり、利益との密接な関係があります。しかし、この仕組みは競争を激化させ、「競争に勝つには借金するしかない」という状況を生み出します。
本書では、この矛盾した構造や、借金によって富がどのように創出されるかについて詳しく解説しています。
金融の黒魔術:こうしてお金は生まれては消える
皆さんは「お金はどのようにして生まれているのか」について正確に答えられますか?意外と知らない人が多い気がします。金融システムは、一見すると魔術的です。よくもまあ、こんなことを考えついたものだと…。起業家は未来から価値を引き出し、それを現在のお金として利用します。しかし、このシステムにはリスクも伴い、一度歯車が逆回転すると大きな混乱を引き起こします。
本書では、この複雑な仕組みとその影響について具体例を交えて説明しています。
労働力とマネー:悪魔が潜むふたつの市場
労働力市場とマネーマーケットには、人間社会に深刻な影響を与える矛盾があります。「狩人のジレンマ」や「予言は自己成就する」といったテーマを通じて、本書はこれら市場が持つ本質的な問題点を浮き彫りにします
機械化と自動化:恐るべき「機械」の呪い
技術革新によって機械化・自動化が進むほど、人々は逆に苦しい状況へ追い込まれることがあります。本書では、大企業による自動化推進とその影響について考察し、「絶望」をもたらす構造的矛盾についても触れています。
新しいお金:収容所のタバコとビットコイン
「お金とは何か。」を考えさせられる章です。収容所内でタバコがお金として使われた事例や、ビットコインによる衝撃的な変化について、本書は具体例を挙げながら解説しています。仮想通貨は従来のお金とは異なる可能性を秘めていますが、その限界や課題も指摘されています。
人類と地球:市場システムによる破壊
人は地球を破壊しながら進歩しています。地球にとって人はウイルスなのでは?という視点から「資本主義と環境問題」について触れています。市場システムは地球環境にも大きな影響を与えます。「愚か者になる競争」や、「すべてを民主化しろ vs 商品化しろ」という対立構造を通じて、本書は持続可能な未来への道筋について思考実験を展開しています。ESG投資などの環境を考えての経済発展は、根本的な解決には至らないことが良く分かります。
本書をオススメする理由
子どもでも経済の仕組みが理解できる!【マネー・リテラシーが身に付く】
本書の最たる特徴として「専門用語を極力排している」という点があります。たとえば、概念として理解しづらい「資本主義」を「市場社会」として、「資本」を「機械」や「生産手段」として置き換えています。訳者である関 美和さん自身もモルガンスタンレー投資銀行などの経歴があるおかげか、優しく適切な日本語で語りかけてくれます。
経済理論や哲学を難しい言葉抜きで語っているので、中学生(個人的には小学校高学年)でも充分に理解でき、楽しく自然と経済の仕組みが理解できるので、本当に必要なマネー・リテラシーが身に付きます。
勉強が苦手な子でも読みやすい一冊だと思います!
読書の習慣がなければ、工夫をして贈ると良いかも!
大人も経済学の入門書としてピッタリ!【自己投資の導入に最適】
子どもに分かりやすいということは、大人にとっては容易な内容になっています。しかし、それがイコール子供向け書籍であるというわけではなく、難しい理論等は苦手だけど学びたいという人の経済入門書として最適であると考えています。株式投資や家計改善だけでなく、ビジネスにおいても必要な知識が身に付くので、子どもへ本書を贈る前に一読する価値は充分にあります。
タイトル以上に大人向けな一冊だと思います。子どもには程よく難しく、大人には程よく易しく書かれています。
子供と自然にお金(経済)の話が出来る【コミュニケーションの潤滑剤】
子どもに書籍を贈ることが難しい場合でも、本書が親子の対話形式で書かれているため、日常のコミュニケーションで「ここはこう伝えてみるか」「この質問にはこう答えれば良いのか」と気づくきっかけになります。こんなに分かりやすく経済について語れる親になりたいものです(個人の感想です)。
具体的なレビューと実際の読者の声
口コミから見る評価
本書に対する口コミを要約すると以下のとおり(ChatGPTによる)。
この本は、経済の仕組みや歴史を、父が娘に語りかけるような平易な文章で解説している点が魅力。農耕で生まれた「余剰」が経済の原点であり、貨幣や借金、格差、さらには環境問題にまでつながる現代の市場社会の構造を、映画『マトリックス』や『ブレードランナー』、収容所でのタバコの取引など具体例を交えて分かりやすく描いています。読みやすさとユーモアが光る一方、後半は考えさせられる内容も多く、再読してじっくり咀嚼すべきという意見も見られます。経済をただの専門領域ではなく、私たち自身が考え、議論するべきテーマとして提示しており、経済学の本質に迫る好書と評価されています。
つまらない、分かりにくいという人も散見されましたが、大半は学びが多い・再読すべきという意見でした。余談ですがChatGPTってすごいですね…。膨大な量のレビューを一瞬で的確に要約してくれた…。
要約文にもありますが、具体例や分かりやすい比喩が多く、子どもにとっては理解しやすい内容となっています。しかし、比喩等が苦手な方には冗長な書籍であるという印象なのかもしれません。あくまでも「父が娘に語る」書籍なので、そのあたりは得意・不得意がありそうです。
※口コミは以下を参考に要約しました。


筆者自身のレビュー・注目ポイント
では、僕個人はどう思うのか。第一印象は「子供に絶対読ませたい」と思いました。
読んでもらえるか否かについては、子の気持ち次第と思います。しかし、今まで多くの書籍を読んできた経験から言うと、これほどまでに分かりやすく、経済という概念やその疑問について網羅しているのは素晴らしいと言わざる得ません。僕自身も学びの多い一冊でした。
そうであるにもかかわらず、値段は1500円(税抜き)であるのだから安いとすら思います。より専門的な書籍では3000円以上は容易にする内容とボリュームであるため、高い本は買えないよ…という方に向けてもオススメしやすいです。
正直…こんな安くていいの?とすら思うの…。
関連書籍のご案内
おすすめの関連経済入門書
より難しい話を簡単に学びたいのであれば、この書籍がオススメです。現在の日銀総裁である植田和男さんによる金融学の図解です。「ざっと学べる」とありますが、本書とは対照的で本は専門用語が多様されており、難しいと感じる人も多いと思います。とはいえ、10時間で学べるというのは嘘偽りなく、本書を読めば経済ニュースがより一層面白いものになることは間違いありません。
上記の本は結構大きいサイズなので、電車の中で読みたいよ!と言う人は文庫版もオススメです。
また、図解があるとより理解しやすいため、以下の書籍も副読本として購入をオススメします。10時間で学びきりたいなら図解必須かも。
子供に語るシリーズが面白い!
マネー・リテラシーとは関係ありませんが、以下の書籍もオススメです。多くのビジネスパーソンが「哲学」の面白さや必要性を認識し始めた昨今。子どもの情操教育に哲学を取り入れるというのは、良い選択肢であると思っています。
まとめ
以上、「父が娘に語る経済の話。」の紹介でした。
何度も繰り返しになってしまいますが、本書は経済学を専門用語を排し、親子の対話形式で分かりやすく解説したユニークな入門書です。著者ヤニス・バルファキス氏は、経済の起源から現代の市場社会、仮想通貨や環境問題まで幅広いテーマを扱いながら、経済が私たちの日常生活とどれほど深く関わっているかを教えてくれます。
本書は、中学生や小学校高学年の子どもでも理解できる内容でありながら、大人にとっても経済学の入門書として非常に有益です。専門的な知識がなくても楽しめる構成であるため、親子で学びたい方や、お金や経済について自然に話せるコミュニケーションツールとしても活用できます。
また、本書の特徴である具体例や比喩を通じて、難解な経済概念を噛み砕いて説明している点は、多くの読者から高評価を得ています。さらに、価格も手頃であるため、自己投資や子どもへの贈り物として最適な一冊です。
「経済」というテーマに初めて触れる方から、改めて基礎を学び直したい方まで幅広い層におすすめできる本書。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか?
~余力があれば以下の記事もオススメです~
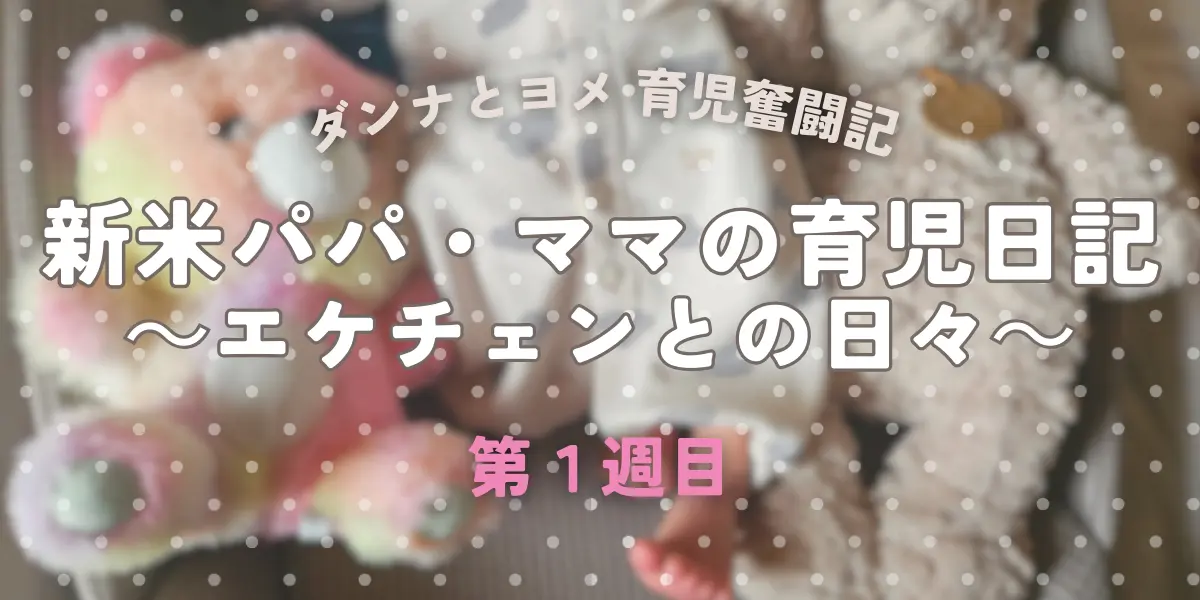
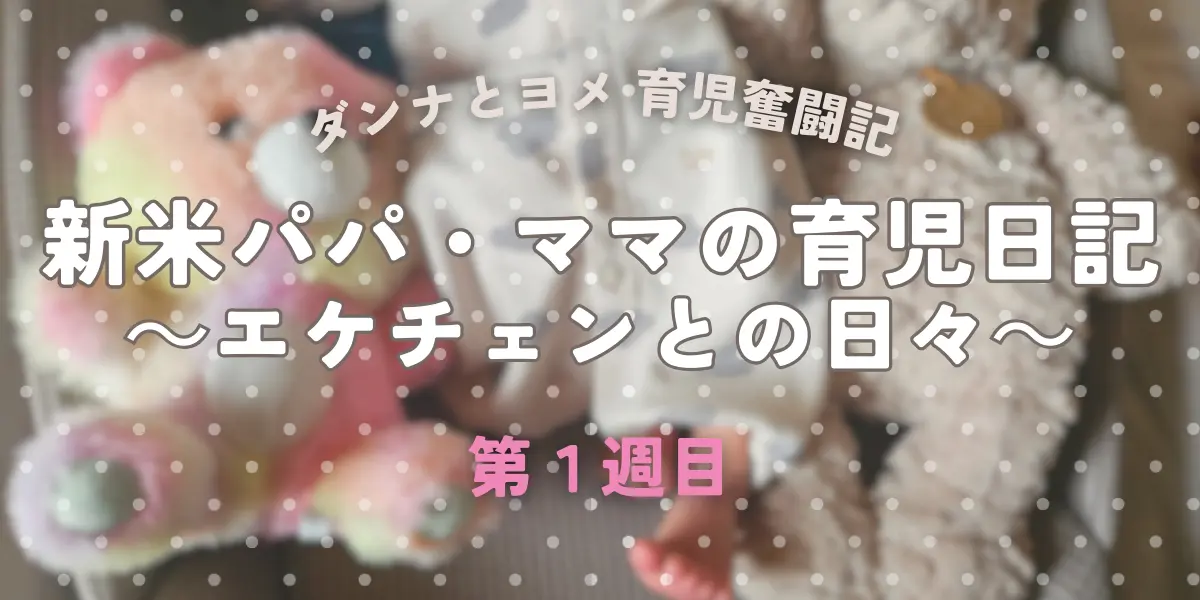
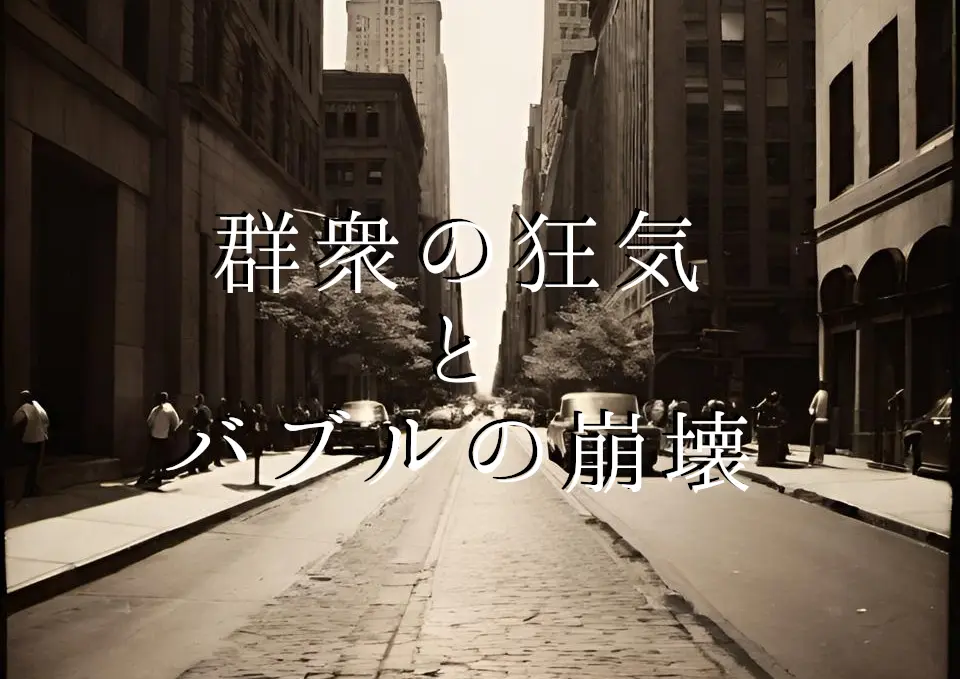
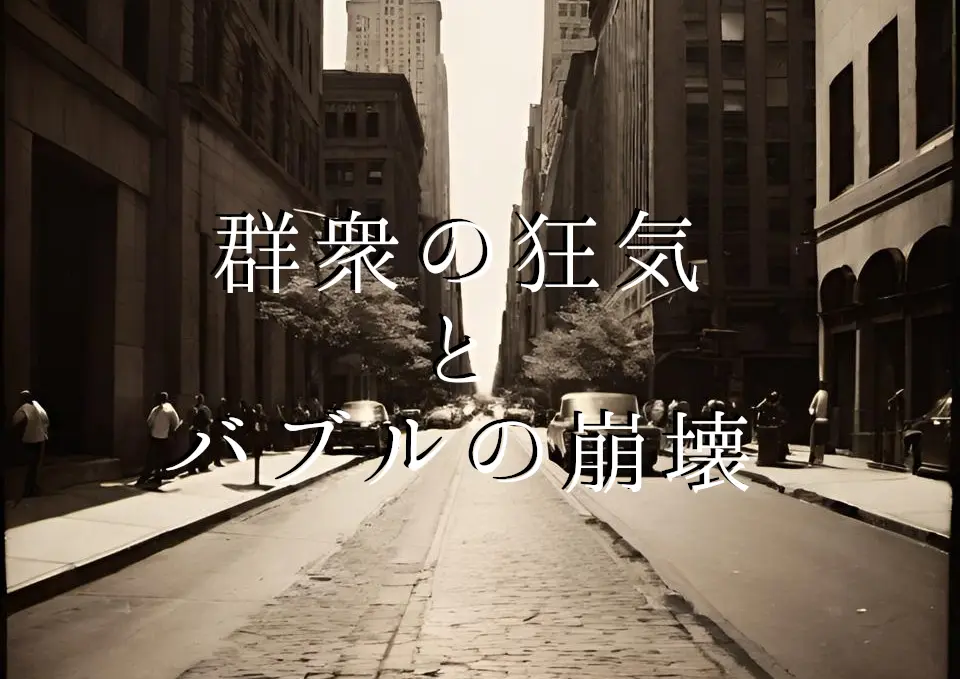
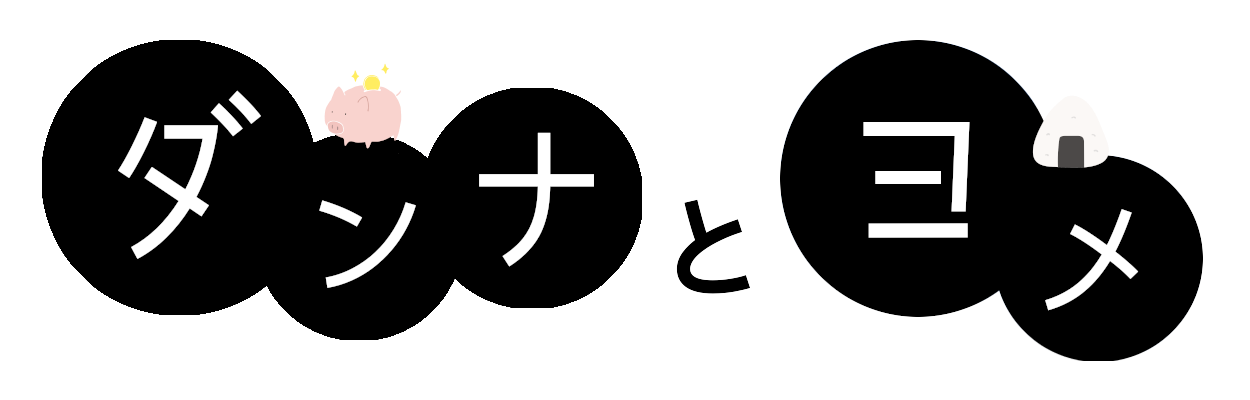

コメント