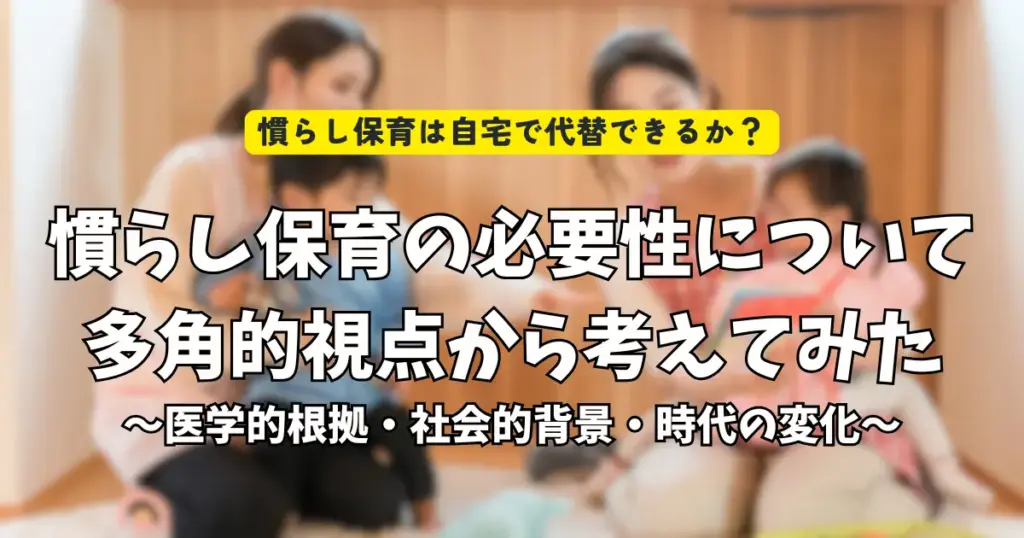
つい先日、SNS上で「慣らし保育は自宅でもできるのでは?」という意見を見かけました。
条件反射的に「自宅で慣らし保育は、自宅で外泊並みに難しいことでは?」と思いました。
しかし、ことの本質は「慣らし保育への提言」ではなく、「海鮮丼を食べに行けるほど余裕がある人に、公金を使うのは如何なものか」という点にあると思います。あくまでも投稿者の意図を汲んで考えた程度ですが。
では、本当に公金を使うべきではないのか?
この記事では、慣らし保育の目的を整理し、医学的根拠・社会的背景・時代の変化の3つの視点からその意義と必要性を検証します。
慣らし保育とは何か
定義と目的
慣らし保育は、乳幼児が保育園という新しい環境に段階的に慣れるためのプロセスです。
初日は短時間(1〜2時間)から始め、1〜2週間ほどかけて通常保育時間へ移行することが多いとされています。目的は、子どもの情緒的安定を保ちながら生活リズムと信頼関係(保護者–保育士)を築くことです。
一般的な目安として1週間〜2週間程度の慣らし期間が多いと思います。
親も子も「離れて過ごす」ことになれる期間ということだね!
日本における一般的な流れ
- 1〜2日目:午前中のみ登園(おやつや昼食前にお迎え)
- 3〜5日目:昼食まで園で過ごす
- 6〜10日目:お昼寝まで経験する
- その後:通常保育時間へ移行
※園・地域・年齢によって運用は異なります。個々の子どもの反応に応じて延長や調整が行われます。
この辺りは保育園によって違うから要チェックだよ
医学的根拠から見る必要性
乳幼児の発達とストレス反応
乳幼児の時期は、脳や感情がぐんぐん育つ大切な時期です。急に環境が変わると体の中で「コルチゾール」というストレスのホルモンが増え、覚える力や気持ちの安定に悪影響が出ることがあります。
妊娠中や赤ちゃんの頃の研究でも、強いストレスがこうした成長に影響する可能性が示されています。そのため、生活の変化は一気に行うよりも少しずつ進めたほうが、体にも心にも負担が少なくて安心と言われています。
分離不安・情緒発達との関連
とくに1〜2歳前後は分離不安が顕著な時期であり、突然の長時間分離は強い不安を引き起こすことがあります。
段階的に保育園での滞在時間を伸ばすことにより、子どもが保育者や環境を「安全」と認識する時間を確保できます。実証研究でも、家庭→集団保育への移行期にコルチゾールの変化が観察される例が報告されており、移行の方法が子どものストレス反応に影響することが示されています。
SIDS(乳幼児突然死症候群)との関係
SIDS(乳幼児突然死症候群)については、未だに何が原因なのか完全な原因究明には至っていません。
しかし、以下の研究によると「預かり初期のSIDS発生は顕著に多く、また発見時のうつ伏せ寝や発症当日体調不良だった児が有意に多かった」とされています。
原因が分かっていないのであれば、出来る限りのことをしてあげるというのが親心という物だと思います。
悲しいことになってからでは遅いからね…。
共働き世帯の現実と慣らし保育
共働きが主流となった社会背景
総務省「労働力調査」の最新データ(2023年)によると、共働き世帯は1,516万世帯、専業主婦世帯は680万世帯で、共働き世帯は専業主婦世帯の約2.3倍に達しています。
このような社会変化を背景に、保育園はもはや「ごく一部の家庭だけが利用する場」ではなく、広く子育て世帯の共通基盤となりつつあります。
インフレや国民負担率増に伴い、ひとりで稼いで家族を養うのが難しい時代になったということかな…?(個人の感想です)
職場復帰と慣らし保育期間の調整課題
多くの保護者は、職場復帰日と慣らし保育期間の調整に苦労しています。
制度上は復帰直前から慣らし保育を始めるのが理想ですが、職場の理解や休暇取得の可否によっては難しい場合もあります。それでも、子どもの適応を優先する重要性は変わりません。
祖父母など家族支援が得られない家庭の増加
核家族化や都市部への人口集中により、祖父母など近距離に住む親族がいない家庭が増えています。このため、家庭内だけで子どもの環境適応をサポートすることはますます困難になっています。
サザエさんのような家族構成は、いまでは逆に珍しくなったよね。
職場復帰との調整課題
理想的には職場復帰前から慣らし期間を設けるのが望ましいものの、実際には休暇取得や職場の理解の度合いに左右されやすく、調整が難しい家庭が多い点は現実的な問題です。
我が家でもどうする~?と悩みの種の一つになっています
時代の変化がもたらす負担と慣らし保育の意味
核家族化・地域支援の希薄化
国勢調査や厚労省の家族関連調査は、三世代同居の減少や単独世帯の増加を示しており、祖父母等の近距離支援が得にくい家庭が増えています。こうした社会構造の変化は、家庭だけで新しい環境への適応を支えることの難しさを高めます。
情報過多と親の負担
インターネットやSNSにより育児情報が氾濫する現在、保護者の判断ストレスが増えています。慣らし保育期間は保育士と直接方針をすり合わせる機会にもなり、その点で家庭単独の「練習」とは異なる価値があると思います。
公金負担と社会的投資
慣らし保育中の保護者が海鮮丼を食べても良いのか?!
育休中や慣らし保育中の保護者が一時的に自分の時間を持つことは、決して無駄ではありません。
慣らし保育は、子どもが新しい環境に慣れるためだけでなく、保護者が心身を整え、これからの生活リズムや働き方に備える期間でもあります。
短い時間でも外で食事をすることは、リフレッシュや気分転換になり、その後の育児や仕事に前向きに向き合う力を取り戻すきっかけになります。保護者が元気で安定していることは、子どもの安心や成長にも直結します。
公的な保育支援は、子どもと保護者の両方が健やかに過ごせるようにするためのものであり、その使い方は「未来への投資」として社会全体にも利益をもたらすのです。
親が安定すれば、会社や周囲の人にとっても有益だよ!
子育て世帯への社会的投資の意義
子育てへの支援は、単なるお金の援助ではなく、未来への投資です。
綺麗ごとは抜きにして、国家存続のためには人口増加が必須であり、それを担う子育て世帯への支援というのは何においても必要である時代となっています。
安心して子どもを育てられる環境があると、子どもは健やかに成長し、学ぶ力や人と関わる力が育ちます。将来その子どもたちが働き、税金を納めることで、社会全体に利益が返ってきます。また、親の負担が減れば、仕事に戻りやすくなり、働き手が増えて経済も元気になります。家族が安定すれば、地域や職場も安心し、みんなにとって暮らしやすい社会につながります。
つまり、子育て世帯を応援することは、今だけでなく、未来の社会をより良くするためのコストパフォーマンスに優れた投資だと言えます。
まとめ
慣らし保育は、子どもが保育園という新しい環境に少しずつ慣れ、安心して過ごせるようにする大事な準備期間です。
医学的にも、急な変化は子どもの心と体に負担をかけることが分かっており、ゆっくり時間を伸ばす方が安心です。
今の時代は共働きが多く、祖父母の助けも得にくい家庭が増えています。だからこそ、保育園での慣らしは家庭だけでは代わりがききません。
また、この期間は親が生活リズムを整えたり、心身を休めたりするための時間でもあります。外で食事をしてリフレッシュすることも、その後の育児や仕事に前向きに向き合う力になると、私は思います。あくまでも個人の感想ですけどね…。
ただ、確実に言えるのは「海鮮丼を食べた」という一点で公金支援の対象外とするのは、慣らし保育の本来の目的を見落としています!
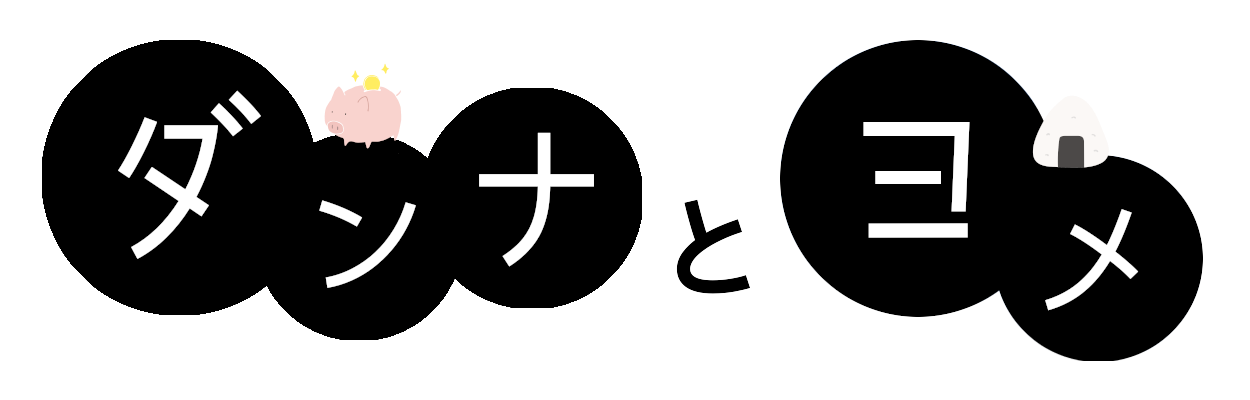

コメント