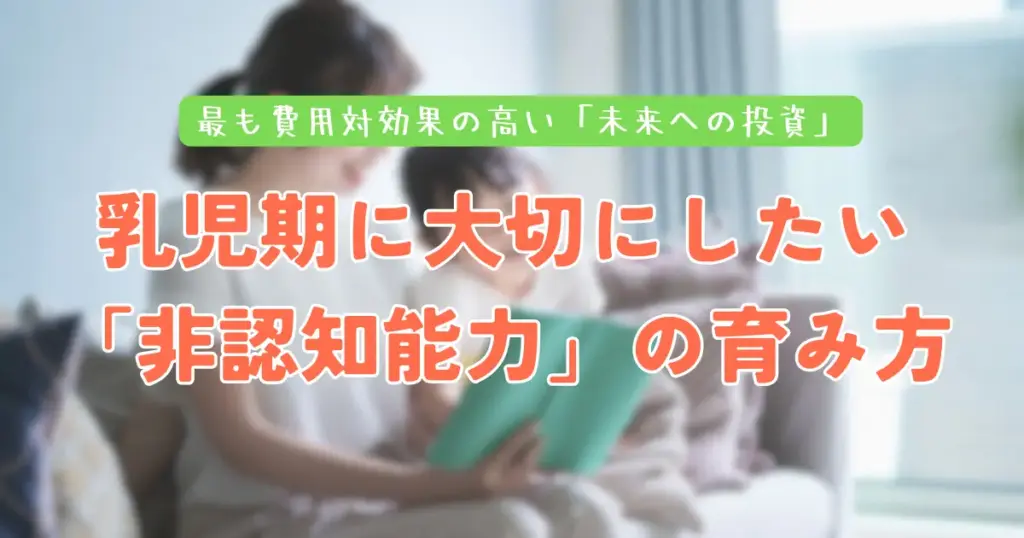
こんにちは、ダンナです。
エケチェンの成長はめまぐるしく、毎日成長が感じられて親として嬉しい一方、この子に僕ら親が出来ることは何だろうと悩んでおります。
今回は乳児教育で重要とされる「非認知能力」について、解説していきます。限りなく誤情報のないように、充分に調べながら纏めましたが、「ここ違うよ!」という御指摘があればコメント等を頂けますと幸いです。
なかなか長いし、理屈っぽいから休み休み読んで下さい!
はじめに|なぜ乳児教育が重要なのか
非認知能力と人生の適応力の関係
近年、「非認知能力」という言葉が教育や子育ての文脈で広く用いられるようになってきました。これは、IQや学力のように数値で測れる「認知能力」ではなく、自己制御力、共感性、やり抜く力、ストレス耐性といった人間の内面的な力を指します。
実はこの非認知能力こそが、将来的な学業成績・社会的成功・メンタルヘルスに深く関係することが、数々の研究で明らかにされてきています。特に、アメリカ・シカゴ大学のジェームズ・ヘックマン教授(ノーベル経済学賞受賞者)の研究では、学力だけでは説明しきれない人生の成功に非認知能力が大きく影響していることが報告されています。
早期教育に焦点が当たる背景
非認知能力は、「教育によって育つ力」であることも大きなポイントです。しかも、それが最も育ちやすいのが乳児期(0~2歳)とされています。この時期は、脳が著しく発達し、人間関係や感情の土台が形成される極めて重要な時期です。
そのため、乳児教育=単なる早期英才教育ではなく、信頼・共感・自己表現の力を育む「環境づくり」と位置づけられます。社会構造が変化し、個人の「人間力」がますます問われる中、乳児期からの非認知能力育成が未来への投資として注目されているのです。
乳児期における「非認知能力」とは何か?
定義:認知能力と非認知能力の違い
認知能力は、読み書き計算など、いわば「テストで測れる力」。一方で、非認知能力は以下のような、テストで数値化するのが難しいが、生涯にわたり必要とされる力です。
- 自己制御力(感情コントロール、注意力)
- グリット(やり抜く力)
- 協調性・共感性
- 動機づけ(学習意欲、内発的モチベーション)
- レジリエンス(回復力、ストレス耐性)
これらは近年、OECDの国際教育指標や、ベネッセ教育総合研究所による国内調査でも重視されています。
非認知能力の具体例と分類(社会情緒的コンピテンスなど)
非認知能力は「社会情緒的スキル」や「ソーシャル・エモーショナル・コンピテンス」とも呼ばれ、以下のように大別されます。
- 自己に関する力(自己認識・自己効力感・情動調整)
- 他者との関係に関する力(思いやり・協調性・感謝・敬意)
- 自他関係を統合する力(社会的判断・自己主張・役割理解)
研究によっては、これらのスキルが生後12ヶ月頃から萌芽的に形成され始めることが明らかにされています。つまり、乳児期からの関わりが後の社会性・学習態度に直結するのです。
乳児期はなぜ「黄金期」なのか
脳の可塑性と神経回路の形成ピーク
乳児期は、脳の「可塑性(柔軟に変化・適応できる性質)」が最も高い時期です。特に、生後0~18ヶ月は、シナプス結合の爆発的増加が見られる敏感期。この時期に多様な刺激を受けることで、将来の思考・感情・行動の基盤となる神経回路が形成されます。
つまり、何を経験するか、誰と関わるか、どんな環境で過ごすかが、将来にわたる人格形成に大きな影響を与えるということです。
赤ちゃんだから分からないだろう…と言うことではないってこと!
アタッチメントと信頼形成の敏感期
特に重要なのが「アタッチメント(愛着)」の形成です。親や養育者との安定した関係は、子どもの自己肯定感や安心感、情緒の安定を生み出します。このアタッチメントは、生後6ヶ月~18ヶ月の間に最も強く形成され、後のストレス耐性や対人スキルに深く関わります。
乳児教育においては、この「関係性を築く力」を中心とした支援が最も重要であり、決して知識のインプットではありません。
以下はアタッチメントについて書いた記事です。参考までに。
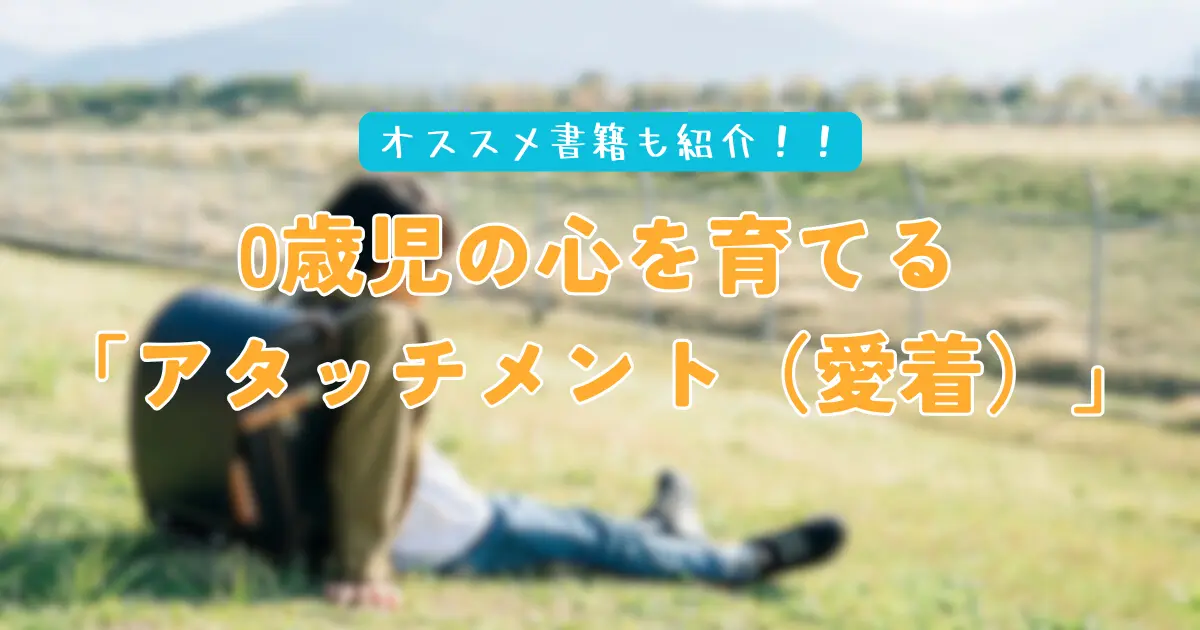
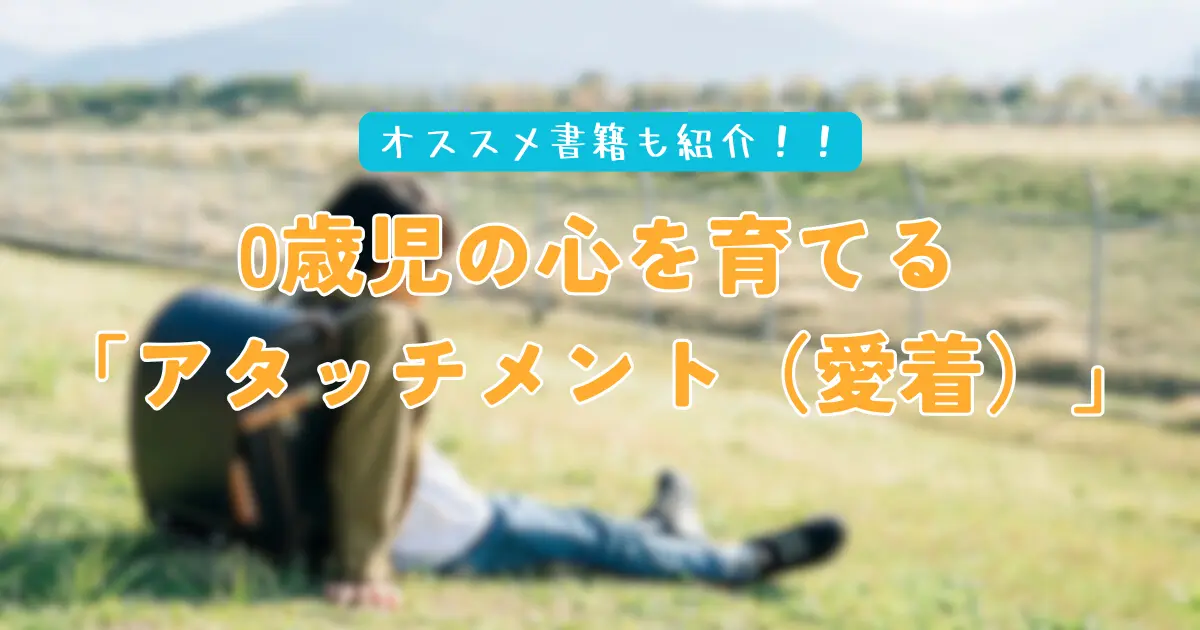
非認知能力の発達と乳児教育の科学的根拠
ペリー就学前計画が示す乳児教育の長期的効果
アメリカ・ミシガン州で1960年代に行われた「ペリー就学前計画」は、非認知能力の重要性を証明した歴史的研究の一つです。教育的リスクを抱える子どもたちを対象に、質の高い就学前教育+家庭への支援を提供し、40年以上にわたる追跡調査を実施しました。
結果は驚くべきものでした。教育を受けた群は、受けていない群に比べて:
- 成人後の高収入・高雇用率
- 犯罪率の低下
- 生活の安定(持ち家率、家庭形成)
さらに注目すべきは、IQには長期的な差が見られなかったにも関わらず、非認知能力が育った群の方が圧倒的に良い人生結果を得ていたという点です。これは、自制心・意欲・社会性といった非認知能力が「人生を変える力」であることを示しています。
OECD・ハーバード大学も注目する「社会情緒的スキル」
OECD(経済協力開発機構)は、2015年に「Skills for Social Progress」というレポートを発表し、「社会情緒的スキル(=非認知能力)」が、well-beingや社会的成功を決定づける力であると明言しました。
また、ハーバード大学の発達科学チームも、「子どもの初期経験が脳の構造と機能に長期的影響を与える」ことを示しており、特に「乳児期に愛着と感情制御を学ぶことが、認知能力を高める土台になる」と強調しています。
非認知能力が将来に及ぼす影響
学業成績だけでなく「人生の満足度」を左右
非認知能力は、学校の成績や試験の得点といった短期的成果だけでなく、生涯にわたるさまざまなアウトカムに関係しています。OECDや国内研究(遠藤, 2017)では、以下のような影響が確認されています:
- 高い自尊感情 → メンタルヘルスの安定
- 協調性 → 良好な人間関係の構築
- 粘り強さ(グリット) → 学習継続・キャリア形成
非認知能力が育まれている子どもは、困難を乗り越える力・失敗から学ぶ姿勢・自律的な行動を身に付けやすく、それが人生の質を高めていくのです。
認知能力との相互作用:スキルがスキルを生む
OECDの報告によると、「非認知スキルが高い子どもほど、その後の認知スキルも高くなる」という結果が出ています。つまり、非認知能力が先に育つことで、学力やIQも伸びるという逆転の発見があるのです。
この現象は「スキルがスキルを生む(Skills beget skills)」と呼ばれ、乳児期の非認知能力育成がいかにその後の発達の好循環を生むかを示しています。
非認知能力の主要スキルと発達プロセス
自己制御力:0歳から始まる「感情のコントロール」
乳児は泣いたり怒ったりすることで感情を外に出しますが、実はこの時期からすでに情動制御の土台が育ち始めています。母親や保育者がその感情にどう反応するかによって、子どもは「落ち着く方法」「気持ちを伝える方法」を学んでいきます。
このスキルは、のちに以下のような場面で活かされます。
- 我慢や順番待ちができる
- 失敗にくじけずに挑戦できる
- 友だちと衝突しても落ち着いて対話できる
共感性と対人関係スキル:心の読み取りは乳児期から
人の表情や声色、仕草を感じ取り、「相手がどう思っているか」を理解する力、これが共感性の始まりです。赤ちゃんは他人の笑顔に反応したり、泣いている人を見て同じように泣いたりすることで、他者との「こころのつながり」を体験していきます。
このスキルが高い子どもは、集団生活でもスムーズに適応しやすく、いじめや排除を回避しやすい傾向があります。
やり抜く力(グリット):目標達成に向けた持続力
乳児期に「何度も挑戦して成功する経験」を積むことで、困難を前にしたときに「諦めない心」が育ちます。例えば、何度も転びながら立ち上がる、積み木が崩れても再度積む――こうした小さな行動の積み重ねが、グリットの発達を支えるのです。
0〜2歳の乳児期にできること
愛着関係を築く:乳児教育の出発点
乳児期における最も重要な教育的要素は、愛着(アタッチメント)の形成です。赤ちゃんが泣いたとき、笑ったとき、不安を感じたときに、保護者が一貫して温かく応答することで、「自分は大切にされている」「世界は安心できる場所だ」という基本的信頼感が芽生えます。
この信頼は、将来的に以下のような力に変換されていきます。
- 感情をコントロールする力
- 他者との良好な人間関係を築く力
- ストレスに対する耐性(レジリエンス)
この段階での「安定した関係性」は、教育というよりも養育環境の質そのものがカギを握ります。
遊びと経験:乳児は「感じる」「動く」で学ぶ
乳児の学びは、五感や身体を使った直接的な経験を通じて進みます。0〜2歳は言葉での理解が難しい時期ですが、感触、音、におい、リズムなどを通じて「世界」を知り、自己と他者の境界を学んでいきます。
以下のような遊びは、非認知能力の発達を自然に促進します。
- スキンシップ遊び(だっこ・ふれあい遊び)
- 鏡を使った遊び(自己認識の芽生え)
- リズム遊び・わらべうた(情緒の安定)
遊びは単なる楽しみではなく、感情・行動・対人スキルを調整する「学びの場」なのです。
保育・家庭教育が果たす役割
大人の「関わり方」が非認知能力を決める
非認知能力の発達は、「どんな親・保育者が、どのように子どもに関わったか」に強く左右されます。重要なのは、子どもの感情を受け止め、反応を返すという双方向のやり取りです。
特に効果的なのは以下の3つです。
- 感情に名前をつけてあげる(例:「悲しかったね」)
- 失敗しても一緒に挑戦を楽しむ(例:「もう一回やってみようか」)
- 共感的な態度(例:「うれしいね、できたね!」)
こうしたやりとりの積み重ねが、子ども自身の自己理解と他者理解の力を育てます。
我が家では「エケチェンは今、”お腹空いたちゃん”なのかな~?」などと問いかけるようにしています。
保育者の専門性と観察力
保育園や幼児教育施設では、保育士の観察力が非認知能力の支援に大きく関与します。たとえば、以下の3つ。
- 他児とのやり取りで泣いた後、どう行動するか
- 一人遊びをどう展開するか
- 自分の思いをどう伝えようとするか
こうした日々の様子から、子どもが持つ非認知的な特性や成長の兆しが読み取れます。保育士が行う記録や対話、遊びの中の関わりは、「評価」ではなく有難い成長のサポートと言うことが分かります。
乳児教育に対する誤解と正しい理解
「早期教育=知識の詰め込み」ではない
乳児教育というと、「英語のフラッシュカード」「お受験用プログラム」など、知識の先取りを強いるものを想像する方も少なくありません。しかし、非認知能力の視点から見た乳児教育とは、そうした方法とはまったく異なります。
非認知能力は、感情・関係性・経験の質によって育まれます。例えば、以下のように、
- 子どもの気持ちを丁寧に受け止める
- 日常の中で成功と失敗を一緒に味わう
- 自己肯定感を支える関わりをする
といったごく自然なやり取りこそが、「教育」とされています。
子ども主体の関わりが真の教育
非認知能力は、「させる教育」ではなく、「寄り添う教育」によって育ちます。子どもが自ら興味を持ち、探求し、挑戦する姿を尊重し支えることが、教育者や保護者の役割とされています。
非認知能力の育成を成功させるには、大人自身が「正解主義」から脱却し、子どもとの信頼関係と共に歩む意識を持つことが何より重要とされています。
そのためにも親が常にゆとりのある環境でいたいですね…(難しい)。
非認知能力と教育格差
社会経済的背景が子どもの発達に影響する
非認知能力は、生まれ持った特性だけでなく、育つ環境や関わる大人の影響を大きく受けます。特に、保護者の経済的・心理的余裕が、子どもの日常体験の質に直結するというデータが国内外で報告されています。
具体的には、
- 保護者のストレスレベルが高いと、子どもの情緒安定に悪影響が出やすい
- 本のある家庭環境や語りかけの量が、言語発達に大きく関与する
- 遊び・外出・体験機会が乏しいと、社会性の発達が遅れる可能性がある
こうした現象は「幼児教育の格差」ではなく、「非認知能力のスタートラインの格差」として顕在化します。
早期支援が格差を是正する鍵になる
OECDやHeckman教授の研究でも繰り返し強調されているのは、乳児期からの介入が最も費用対効果が高いということです。
貧困層の子どもへの支援プログラムを通じて、以下のような成果が出ています。
- 学校適応の向上
- 行動問題の減少
- 保護者の養育態度の改善
このように、非認知能力を育む支援が「教育格差の連鎖」を断ち切る力を持つことが、多くの研究によって証明されつつあります。
まあ、まだ否定的な意見もあるので「されつつある」に留めています。
行政・地域の取り組みと支援体制
日本における非認知能力支援政策の現状
日本でも近年、非認知能力への関心が高まりつつあります。文部科学省は「幼児教育振興法」に基づき、幼児期における「生きる力の基礎」の育成を推進しています。また、内閣府の「子ども・子育て支援新制度」では、0〜2歳の保育無償化などの施策を通じて早期支援体制が強化されています。
とはいえ、以下のような課題も残ります。
- 非認知能力の明確なカリキュラム化の遅れ
- 保育士・教育者の専門研修機会の不足
- 地域間による支援格差
このような背景から、より一貫した政策と人材育成が急務とされています。
まあ、この辺りは難しい課題だな~と感じています。頼りになるのは臨床心理士か…。
地域連携と保護者支援が未来を変える
非認知能力の育成には、行政だけでなく地域社会との連携が不可欠です。具体的には、
- 地域子育て支援拠点(子育て広場、子育てサロン)
- 児童館や家庭訪問による養育支援
- NPO・ボランティアによる居場所提供
また、保護者自身が育児について学び、支援を受けられる環境が整っていなければ、教育効果は限定的になってしまいます。
地域の中で「共育(ともに育つ)」という意識を育てることが、持続可能な乳児教育の鍵になるのです。
調べてみると児童館や図書館などの公的施設で学ぶ機会が提供されているので、自分の地域はどうかな?と調べてみて下さい!
非認知能力の測定と科学的検証の動向
非認知能力は「測れない」わけではない
一見「数値化が難しい」とされる非認知能力ですが、心理学や発達科学の分野では、観察・質問紙・行動実験など多様な方法で測定が行われています。
たとえば以下のような評価が可能です。
- 感情調整力:保育者の行動観察、表情の読み取り力など
- 自己制御力:自己報告式テスト、タスク遂行時間の計測
- 共感性・対人スキル:社会的ジレンマ場面での行動観察
OECDの国際調査でも、これらのスキルが統計的に測定可能であり、将来の社会的適応を予測できることが確認されています。
科学的検証に基づく教育プログラムの開発へ
今後の教育では、「経験的に良さそうな育て方」ではなく、科学的なエビデンスに基づく乳児教育プログラムが求められます。
日本でも、文部科学省や国立教育政策研究所によって、以下のような動きが進んでいます。
- 乳児期における社会情緒的コンピテンスの発達指標の構築
- 発達段階ごとの教育介入の効果測定
- 家庭・保育園・地域をつなぐ教育ネットワークの設計
このように、非認知能力は単なる流行の概念ではなく、今や教育政策・心理学・社会学の交差点にある核心的テーマとなっているのです。
家庭と社会に求められる乳児教育支援
保護者の「孤育て」を防ぐ社会的ネットワーク
近年の子育て環境では、核家族化や地域のつながりの希薄化により、保護者が孤立した状態で育児にあたる「孤育て」が問題となっています。この状態では、子どもの情緒や非認知能力を支える「安心感」や「共感的関係」が構築されにくくなってしまいます。
そのため、保護者が気軽に相談でき、育児の悩みを共有できる場として、以下のような支援が求められます。
- 地域の子育てサロン・広場の活用
- LINEやSNSを通じた育児コミュニティの構築
- 保育園・小児科・行政機関による連携的支援
子ども・家庭・地域をつなぐ「共育」視点
非認知能力の育成は、家庭の中だけで完結するものではありません。「大人同士のつながり」が、子どもの育ちを支える土壌になるのです。親同士が助け合い、地域の大人が子どもに関わり、保育士や行政とつながる――このような「共育(ともいく)」の環境が重要です。
地域全体が「子どもは社会の宝」であるという意識を持つこと。それこそが、乳児教育の真の充実につながるのです。
新潟では熱心に共育について発信・推進しているんだよ!すごいぞ!新潟!!(新潟贔屓です)
まとめ|乳児教育は未来への最良の投資
非認知能力は「生きる力」の土台
本記事を通して繰り返し述べてきたように、乳児期は非認知能力の発達における「ゴールデンタイム」です。この時期に築かれた愛着・信頼・自信・共感は、その後の認知能力すらも支え、人生全体の幸福度や社会的適応力に影響を与えるとされています。
教育の原点は「関係性」である
乳児教育とは、知識やスキルの詰め込みではなく、人としての根本的な力を育むための関係性づくりです。だからこそ、保護者や保育者がどのように子どもに関わり、社会がそれをどう支えるかが極めて重要になると考えられています。
未来を変える「乳児教育」のチカラ
非認知能力の支援は、社会的格差の是正にもつながり、将来の犯罪率や医療費の抑制などにも寄与します。まさに、最も費用対効果が高い「未来への投資」なのです。
私たち一人ひとりがこの事実に気づき、日常の中でできる支援を少しずつ実行することで、すべての子どもがその力を最大限に発揮できる社会が実現していくと願っています。
以上、愛するエケチェンのために調べてまとめた記事でした!
関連書籍
家庭教育が重要『「非認知能力」の育て方 心の強い幸せな子になる0~10歳の家庭教育』
読みやすく、網羅的に書かれている一冊。もう一度、非認知能力について学びたいな~と言う方にオススメできる一冊です。これを読むことも子供の未来にとり最適な投資と言えます。
一人で悩まず誰かに倣う『非認知能力を育てる あそびのレシピ』
子供と遊ぶといっても個人では限界があります。遊びのレパートリーが無限に出てくるのは保育士さん方くらい。
ならばと我々が出来るのは誰かに倣うことではないでしょうか。かわいいイラストで解説されているので、読むだけでも癒されます。
育児が大変で追いつかないなら『マンガでやさしくわかる非認知能力の伸ばし方』
本来であれば、何かを学ぶのであれば活字で読むことを強くオススメしています。
しかし、毎日慣れない育児でへとへとなパパママ。まずは手軽に学ぶのことは、別に悪いことではないと思います。だって、毎日親だって頑張っているんだもの…。
いずれ上記の書籍等を読んで、しっかりとした知識を身に着けられれば良いのではないでしょうか。
導入のまえの、入門のまえの、味見として是非。
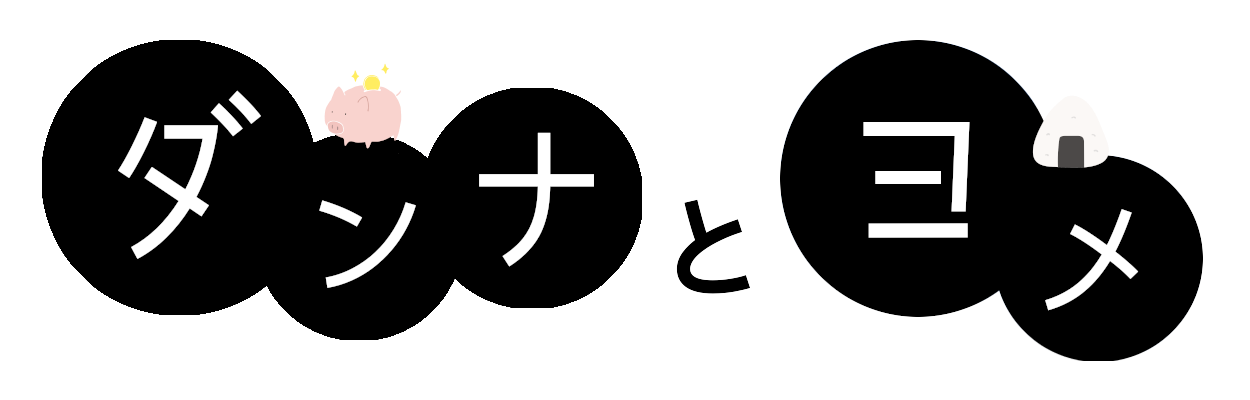

コメント