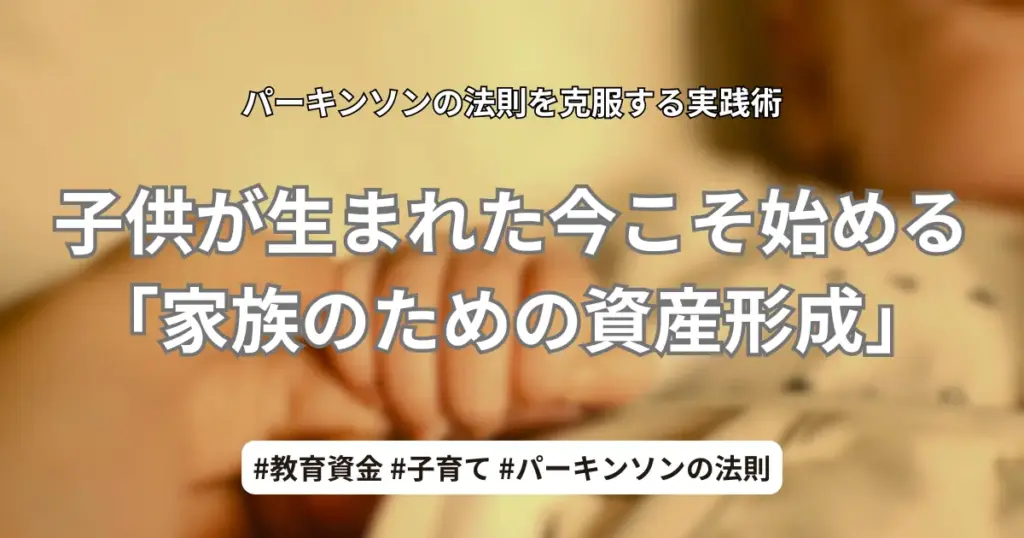
記事の概要:子供が生まれた今だからこそ、資産形成の「基本」を再定義する
こんにちは、ダンナです。
私事ですが、先日無事に第一子が誕生しました。とにかく幸せです。
この小さな命を抱いたとき、強烈に感じたことがあります。それは「この幸せを守り抜くには、盤石な経済基盤が必要不可欠だ」という現実的な責任感です。
「もしもの備え」は、独り身のときとは比べ物にならないほど重みを増しました。そこで今回は、子供が生まれた私が改めて実践している「経済的安定を手に入れるための具体的な思考法とアクション」について共有します。
これから子育てが始まる方、あるいは将来への漠然とした不安を「具体的な安心」に変えたい方の一助となれば幸いです。
※記事内にはアフィリエイトリンクを含みます。もし記事が参考になり、リンク経由でお買い物いただければ、全額を我が子のオムツ・ミルク代として大切に使わせていただきます!
「収入が増えても貯まらない」恐怖の法則を断ち切る
お金を増やすために最も重要なのは、投資テクニック以前に「支出の管理」です。どれだけ稼いでも、バケツの底に穴が空いていれば水は溜まりません。
ここで意識すべきなのが、シリル・ノースコート・パーキンソンが提唱した「パーキンソンの法則」です。
支出の額は、収入の額に達するまで膨張する
パーキンソンの第2法則
これは本当に恐ろしい法則です。昇給したはずなのに、なぜか貯金額が変わっていない…という経験はありませんか?新卒の頃は手取り10数万で生活できていたのに、収入が増えた今は生活水準もいつの間にか上がり、結局ギリギリの生活をしている。これがパーキンソンの法則の正体です。
私が実践する「法則」への対抗策
子供が生まれると支出は必然的に増えます。だからこそ、意識的にこの法則に抗う必要があります。私が実践している対抗策は以下の3つです。
①「先取り貯蓄」による強制リセット
パーキンソンの法則を無効化する唯一の方法は、「最初からなかったことにする」ことです。
給料が入った瞬間に、貯蓄・投資分を別口座へ自動送金させます。残ったお金だけで生活すれば、法則は発動しようがありません。
児童手当とかの臨時収入も全部貯蓄しているよ!
② クレジットカードの「痛み」を知る
2001年の研究(Prelec & Simester)によれば、クレジットカード払いは現金払いに比べて「支払いの痛み」を感じにくく、支出が増えやすいとされています。
もし「貯金が苦手だ」と感じているなら、一度「現金管理(またはデビットカード)」に戻してみてください。物理的にお金が減る感覚を取り戻すことで、無駄遣いは劇的に減ります。
我が家の生活費は面倒だけど”現金”で支払っているよ。そちらの方が「痛み」があるからね!
③ 固定費の断捨離
スマホ、保険、サブスク。これらは一度契約すると「空気」のように支出され続けます。子供が生まれたタイミングこそ、見直しのベストタイミングです。
【資産形成チェックリスト】
あなたはいくつ当てはまりますか?
- □ 家計簿アプリ等で収支を可視化している
- □ 使途不明金が月5,000円以下だ
- □ 貯蓄・投資は「自動引き落とし」にしている
- □ サブスクの棚卸しを3ヶ月以内に実施した
- □ 浪費(自分へのご褒美)予算の上限を決めている
「守るものができた」今のリスク許容度を知る
独身時代と親になってからでは、取れるリスクの大きさが変わります。
リスク許容度とは、簡単に言えば「最悪の場合、資産がいくら減っても生活とメンタルが破綻しないか」という指標です。
詳しくは以下の記事でも解説していますが、今回は「親としての視点」で補足します。
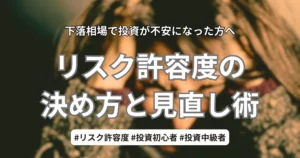
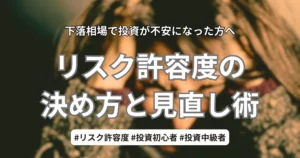
子育て世代の投資戦略:3つの柱
私は現在、リスク許容度の上限いっぱいまで投資を行っていますが、それは以下の戦略で「心の安定」を確保しているからです。
- 時間の分散(積立投資):
「いつ買うか」を悩みたくありません。子供との時間を最優先したいからです。ドルコスト平均法は、相場の変動に一喜一憂しないための「精神安定剤」としても機能します。 - 資産の分散(オールカントリー/S&P500 + α):
株式一本足打法は、暴落時に家族を不安にさせます。債券やゴールド(金)なども視野に入れ、どんな天候でも進めるポートフォリオを意識しています。 - 現金の確保(生活防衛資金):
投資資金とは別に、生活費の6ヶ月〜1年分は必ず現金で確保しています。これがあるからこそ、投資でリスクを取れるのです。
「高配当株投資 vs インデックス投資」論争などもありますが、重要なのは「自分が夜ぐっすり眠れる配分かどうか」です。家族を守るための投資で、自分がストレスを感じては本末転倒ですから。
30年先を見据えた「雪だるま式」資産形成
我が子が成人し、社会に出るまでの20年、あるいは私たちが老後を迎える30年後。そこを見据えた長期投資こそが最適解です。
最適解としての「eMAXIS Slim」シリーズ
金融工学の観点からも、長期的なインデックス投資が合理的であることは証明されつつあります。これから始めるなら、手数料が圧倒的に安い以下のファンドが「60点〜80点」を確実に取れる選択肢です。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー):これ一本で世界中に投資。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):経済大国アメリカの成長に乗る。
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型):株式だけでなく債券等も含みリスクを抑える。
私はS&P500を中心に据えつつ、自分のリスク許容度に合わせてサテライト的に高配当株やゴールドを組み込んでいます。100点満点の投資を目指して疲弊するより、80点の投資を30年続ける方が、結果的に大きな資産になります。
ぼくはETFでも教育資金を準備しているよ!


情報をアップデートし続ける(パパの自己投資)
最後に。資産形成において「情報」は武器です。しかし、SNSの断片的な情報に踊らされてはいけません。
私が自信を持っておすすめできる、体系的に学べる書籍を紹介します。これらは私の投資スタンスの根幹を作ってくれた本たちです。
投資の「型」を身につける入門書
投資の勉強をするうえで、この本は外せません。投資初心者の人には必ずオススメしている一冊です。
自分という資本をどう運用するか
所謂、自己啓発本とは異なり論理的に人的資本の運用について書かれています。値段相応の価値がある。
投資の本質を知る良書(中上級者向け)
この本を読んだからと言って投資が上手くなるわけでもありませんが、物事のはじまりを理解すると、今自分が何をしているのか理解できます。インデックスファンドの本質を知ることができる良書です。
まとめ:家族のために、今日から動こう
子供が生まれて改めて思いますが、資産形成は「自分の贅沢のため」ではなく、「家族の選択肢を増やすため」のものです。
パーキンソンの法則に負けず支出を最適化し、リスクを管理しながら淡々と市場に居続ける。地味ですが、これが最強の親の愛情表現の一つかもしれません。
毎月の収支確認(我が家では「決算」と呼んでいます)など、小さな一歩から始めてみませんか?
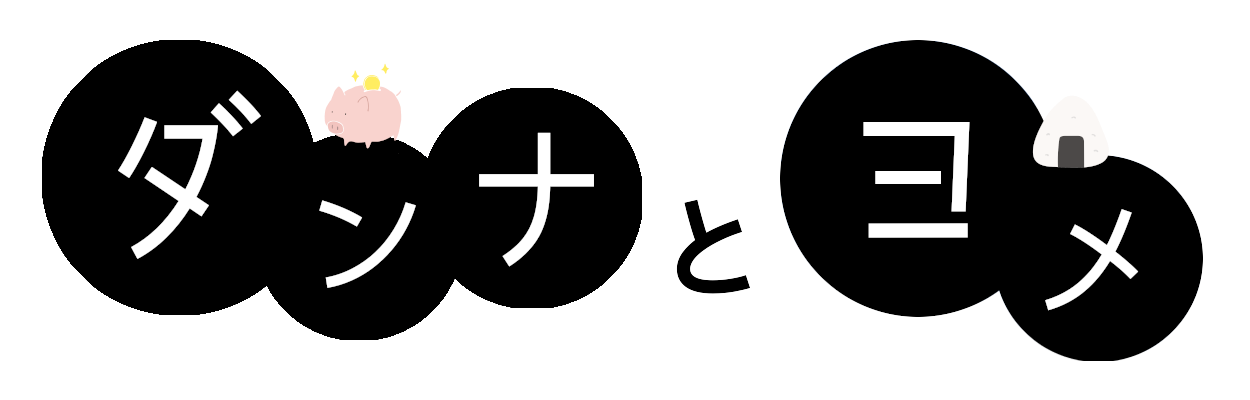

コメント