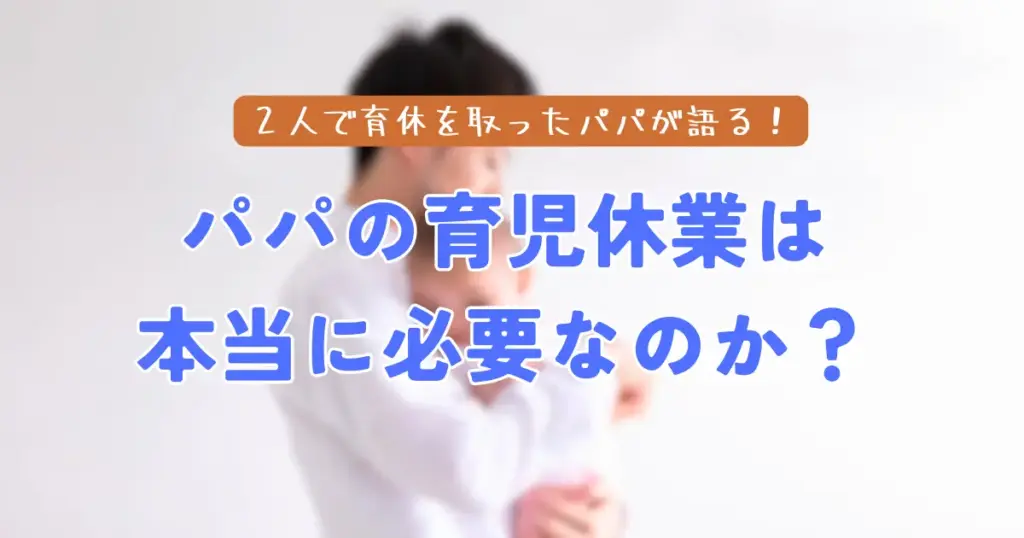
こんにちは、ダンナです。
育児休業を取得してから約4か月が経ちました。はやいな~…。楽しいことも大変なことも色々あったな~…。まだ4か月だけど…。
さて、今回は実体験に基づき、以下の3点に焦点を当てて説明していきます。
- 男性が育児休業を取得する意味はあるのか
- 育休を取得しても収入は大丈夫なのか
- 育休を取得したメリット・デメリット
育休を取得しようとしているパパさん、育休を取得して欲しいけど説得が難しそうなママさんの一助になれば幸いです。
ダンナの育休取得状況について
夫婦共に育児休業は1年間取得した
私たち夫婦は、夫婦共に1年間の育児休業を取得しました。これはなかなか珍しいケースかもしれません。
多くの場合、ママだけが長期の育休を取ることが多いですが、夫婦で同時に取得することで「育児のスタートを2人で迎える」ことができました。
特に新生児期は、授乳やおむつ替え、夜泣き対応など、心身ともに負担がかかる時期です。ここをワンオペでなく“チーム育児”として乗り越えられたのは、本当に大きな意味がありました。
会社への申請は、ややハードルが高かったとおもいます。比較的取得しやすいと言われる弊社でもハードルが高いと思えたので、まだまだ理解が得にくい会社では一苦労あるという認識だけはママさん側でも理解していただけると嬉しいです。
とはいえ、制度としては男性も1年間の育休取得が可能です。実際に取得してみて、「もっと多くの男性が当たり前に育休を取れる社会になってほしい」と強く感じています。
というそれらしい理由をつけたけど、仕事を忘れヨメと過ごしたかったんだよね…。ヨメ大好きだから。
里帰り出産のために新潟へ
また、我々は里帰り出産をしました。初産と言うこともあり、ヨメ両親の”近くで”子育てをすることで、産後の精神状態も落ち着くかな~という理由です。不安いっぱいだしね…。
東京→新潟→東京と引っ越しをしたため、恐らくは普通の育休取得者よりも費用や労力が掛かっています。しばらく東京に住まないなら、引き払ってしまった方が経済的だったので…。
いまでも里帰り出産は後悔していないよ!寧ろ良い経験が出来た…。
男性が育児休業を取得する意味
「男性が育児休業を取る意味ってあるの?」と、よく耳にする疑問。私自身も「男が1年も取る意味ない。暇になる。」という指摘を内外から言われてきました。
しかし、実際に育児休業を取得してみて感じたのは、“意味しかない”ということ。ここでは、その具体的な理由を3つに分けて紹介します。
今まで頑張ったパートナーをサポートできる
まず何より伝えたいのは、十月十日も頑張ってくれて、出産という命がけの大仕事を終えたパートナーに、しっかりと寄り添うことが出来る。何においてもこれが最重要ではないでしょうか。
食べるものも制限され、睡眠も妨害され、体調が乱れ、手入れしていた髪や肌は荒れ、何よりもずっとお腹の中で命を育み守ってくれていました。
頑張ったパートナーに対して、僕ら男性が出来ることは育休を取得して支えることだと思います。
経済的に~…など、色んな支え方があるだろうけど、僕は母子ともに健康でいてほしいので、育休と言う方法で支えることにしたよ。
育児の不安を夫婦で共有・軽減できる
新生児との生活は、予想以上に不安の連続です。「ちゃんと母乳飲めてる?」「この泣き方、病気じゃない?」「夜ぜんぜん寝ない…」と、初めてのことだらけです。
そんな時、夫婦のどちらかだけが負担を背負ってしまうと、心が持ちません。でも、2人で一緒に向き合うと、自然と気持ちの余裕が生まれます。「一緒に悩んでくれてる」「一緒に育ててる」この感覚がとても大切だと感じています。
「楽しさ10割、つらさ0割」と常に言っているダンナですが、それでもしんどいな~というときもしばしば。
例えば、肌に突然恐ろしい程の湿疹が現れたり(乳児湿疹)、うんちが出なくて叫ぶように泣いたり、何で泣いているのか分からなくなったり…本当にもう大変でした。
また、1~2時間おきに授乳(又は粉ミルク)を与えなければならないので、こちらも永遠と寝不足状態が続きます。3か月までは纏まって寝れませんでした。
今振り返っても、これをヨメ一人にお願いするなんて出来ません。
「一日育児より、夜間育児・日中仕事の方が楽」と同僚が言っていた理由が分かりました。
生活リズムを家族で一緒に作れる
育休中に特にありがたかったのが、子あり家族としての生活リズムを一緒に作れる時間があったことです。
子どもが生まれると、当然ながら生活は一変します。深夜に起きる、日中は短いスパンで授乳・オムツ替え・抱っこのループ。そんな不規則な日々の中で、どうやって(何時に)食事をとるか、いつ家事を回すか、どのタイミングで休息をとるか。これらを夫婦で模索する時間が取れたのは本当に貴重でした。
二人いたことで「この家事は僕がやるから今日は寝ときな」と、僕も眠い状態ですがヨメ優先に休ませることが出来ました。ヨメの身体は目に見えませんが、ボロボロに傷ついていたので…。
この経験を通して、今後の育児や家事の分担について改めて話し合えたのも大きなメリットだと感じています。
苦楽を共にして、同じ視点に立つことが重要だと思うヨ!
育児休業を取得した場合の収入と支出について
「育休を取りたいけど、収入が減るのが不安…」という声は、育休取得を迷う男性の中で最も多い悩みの一つです。
私は子どもを授かる前から資産形成に努めていたため、そこまで大きな負担はありませんでした。それでも正直な話、収入が減ること、今後かかる費用が未知数であることなど不安でいっぱいでした。
それでも、制度を理解すれば「意外と何とかなる」と思える部分も多いと実感しました。
ここでは、育児休業中のお金に関するリアルな情報をお伝えします。
資産形成については以下のカテゴリーをどうぞ
育児休業給付金は2か月ごとに支給される
まず大前提として、育児休業中は無給になる場合がほとんどですが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。この給付金があるからこそ、育休中の生活を安心して維持できていると思います
支給は基本的に2か月ごと。例えば、4月と5月分が6月上旬に振り込まれる…というようなサイクルになります。つまり、初回の振り込みまでに少し時間が空くため、最初の1〜2か月分は自分で備えておくことが大切です。
会社の申請タイミングやハローワークによって差があるそうなので、会社に聞いてみよう!
最初の半年は「手取りの約67%」支給で思ったより減らない
育児休業給付金の金額は、最初の6か月間は休業前の月給(手取りではなく総支給額)の約67%が支給されます。これは、実際の手取りに近い金額になります。夫婦ともに育休をとるなら、28日間分だけですが13%が追加で付与されるため、1か月分は100%支給です。
たとえば、月収30万円(手取り24万円程度)の人であれば、給付金として月20万円前後が支給されることになります。多少の減収にはなりますが、家計を見直せば大きく生活を崩すことはありませんでした。
また、社会保険料(健康保険や厚生年金など)は免除されるため、手取り収入と比較すると差が縮まります。
子育ての支出は毎月4~5万円を目安にすると余裕がある
新生児~乳児期にかかる費用としては、主に以下のような項目があります。
- おむつ・おしりふき
- 粉ミルクや哺乳瓶関連
- 衣類や肌着(季節ごとに変わる)
- ベビーベッド、チャイルドシートなど初期投資
- 定期健診・予防接種の交通費や医療費(助成制度も活用)
これらを踏まえて、毎月の育児費用は平均して4〜5万円を目安にすると、比較的ゆとりを持って対応できる印象です。
もちろん、ミルク育児か母乳育児か、消耗品をどこで買うか、セールや中古品を活用するかなどによって変わりますが、「予算の枠を決めておく」と家計管理がかなり楽になります。
我々はネットで買うことが多いです。肉体的負担が減ると、精神的ゆとりが生まれるため、楽しく子育てをするなら…と言う理由もありますが、ネットと店頭で値段が大きく違わなかったというのも理由です。
とくに、おしりふきは無限に必要です。なんにでも使えるのであって困ることは有りません。それなのに重いので、ネット購入推奨品です。
育休を取得したメリット・デメリット
育児休業を実際に取得して感じたのは、「メリットが想像以上に大きい」ということです。
もちろん、全てが順風満帆というわけではなく、現実的なデメリットもあります。ここでは、私の実体験をもとに、育休を取ることのメリットとデメリットを整理してみました。
育休のメリットは無限大!
子どもの成長を間近で見られる
一番のメリットは、子どもの成長をリアルタイムで見守れること。寝返り、笑顔、初めての声出し、首すわり…といった“初めて”の瞬間に立ち会えるのは、本当に貴重な体験です。
仕事で忙しくしていたら見逃していたであろう瞬間を、毎日の中で自然に迎えられることは、人生の中でも特別な時間になると思います。
寝返りをうつ瞬間に立ち会えた時は、大学合格以上に嬉しかったよ…。大声出ちゃった…。(そのせいでエケチェンが泣いた)
子有り状態の家事分担について理解し合える
育児を始めると、それまでの家事のやり方やバランスがまったく通用しなくなることがあります。
「抱っこしてる間に手の込んだ料理は難しい」「オムツ替えで食器洗いが中断される」など、予期せぬことが日常茶飯事です。
この混乱期を夫婦で一緒に過ごすことで、育児と家事がどれほど大変かをお互いに理解し合えるようになりました。その結果、家事分担の“納得度”が上がり、無用なストレスも減りました。
ダンナは洗濯が苦手…。それ以外全部やった方が気が楽…。
ヨメは洗濯の方が楽…。それ以外をやってくれるなら喜んでやる…。
勿論、ダンナも洗濯はするし、ヨメもそれ以外の家事は完ぺきにこなします。素敵なヨメです。愛してる…。
ここで言いたいのは、お互いに苦手な家事を把握しておくことで、自然と家事の分担が出来るようになりました。バランスが悪いな~と思ったら、そこは家族なので都度都度話し合えば良いだけのこと。
親子の絆(ベビーボンディング)を深められる
「ベビーボンディング」とは、親と子の間に築かれる深い情緒的なつながりのことです。
新生児期~乳幼児期に親がそばにいることで、愛着形成(アタッチメント)が促進され、子どもの情緒的安定や自立心の基盤づくりに大きく寄与すると言われています。
育休を取って四六時中そばにいることで、赤ちゃんも私の声や存在に安心してくれるようになり、「父としての自覚」が一気に芽生えた瞬間でもありました。
エケチェンのこと、一日中眺めていても飽きないよ…!
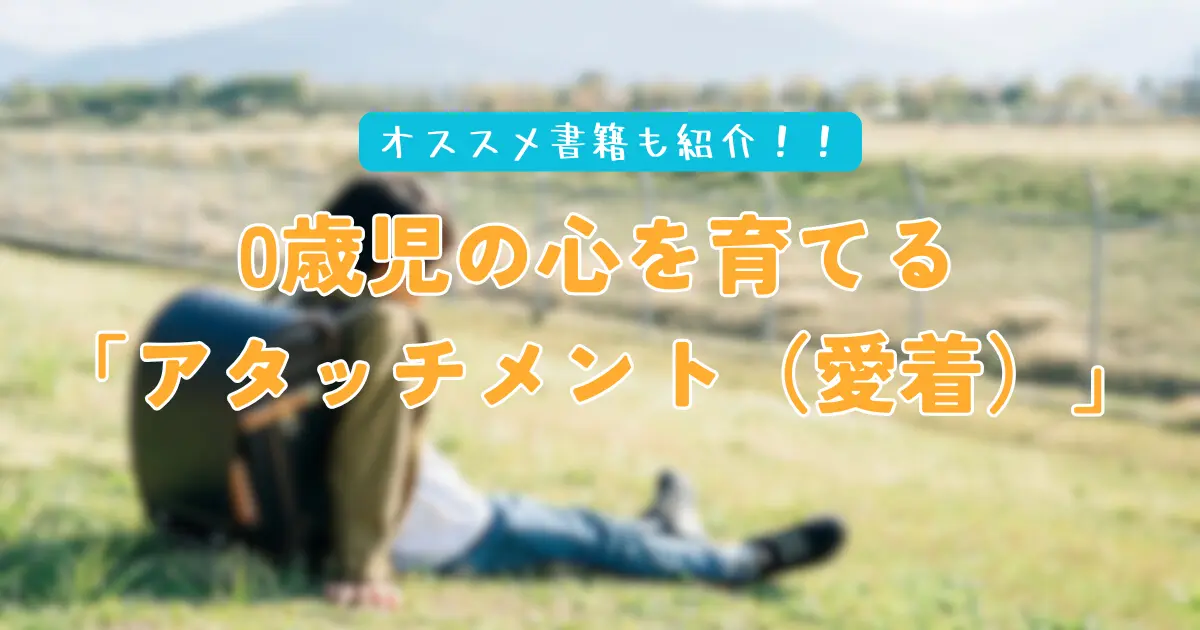
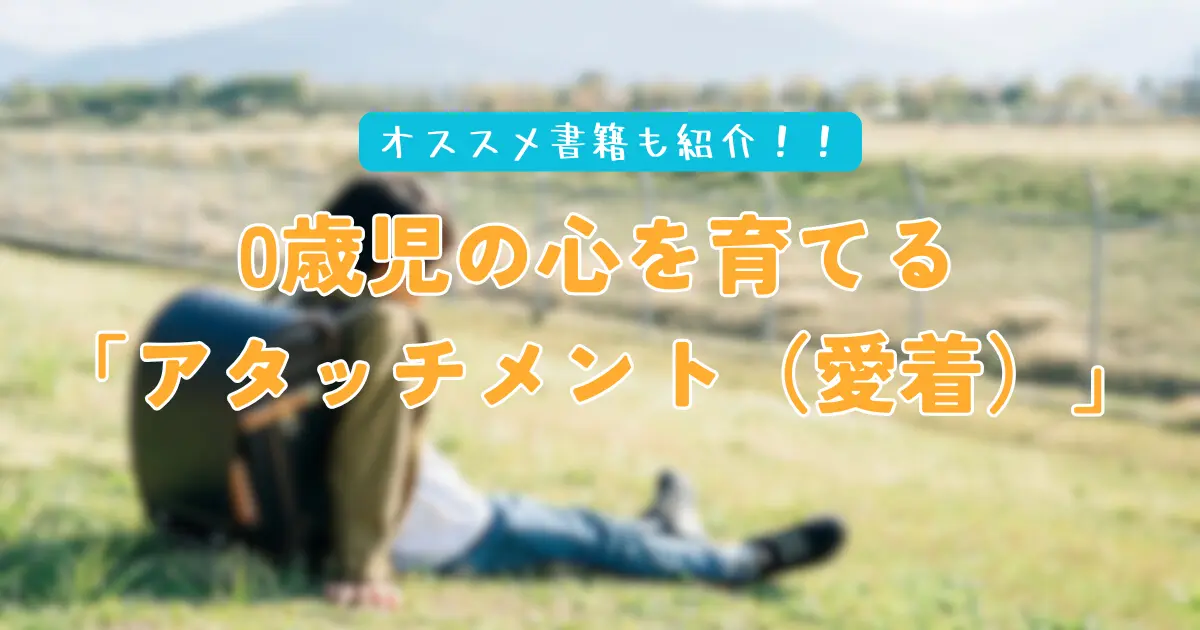
育児に専念できることで心身の負担を軽減
仕事と育児の両立は、時間も体力も想像以上に大変です。育休中は、そうした“タスクの分散”から離れ、育児にだけ集中できる環境が手に入ります。
どちらかが料理している間は、子どもと楽しく絵本を読んだり、遊んだりできます。この時間が本当に幸せなんだ…。
また、自分のペースで授乳・おむつ替え・寝かしつけができることで、精神的なストレスもぐっと軽減されました。特に睡眠不足が慢性化する育児中には、心身のケアが本当に大切です。
寝不足によるストレスは想像の1000倍きついですよ…。
子どもの発達・健康管理をきめ細かくサポート
まだまだ地球人になりたての赤ちゃん。定期健診や予防接種、発熱時の受診など、乳幼児期は何かと医療関連の予定が多い時期です。
育休中であれば、これらを慌てることなくこなすことができ、ちょっとした体調の変化にもすぐ気づくことができます。結果として、トラブルを早めに対処できる環境が整い、子どもにとっても安心な毎日になります。
我々はおやつタイムに「今後の予定」について話し合っているよ
とはいえ現実的なデメリットも…
育休に入るまでが大変
育休を取ること自体に、まだまだ社会的な“壁”を感じる場面がありました。職場の上司や同僚の理解、仕事の引き継ぎなど、取得までに乗り越えるべきハードルが多いのが現実です。これでも比較的取得しやすい会社と言われています。
特に男性の場合、「本当に必要なの?」「会社に迷惑じゃない?」という空気感が残っている職場もあるでしょう。そうした風潮に一石を投じる意味でも、一人ひとりの実践が大事だと感じました。
僕は数年前から、1年以上育休取りますねと公言していたよ!
収入は一時的に途絶える
前章で触れたとおり、育児休業給付金はあるものの、育休中は基本的に無給となります。また、給付金の支給も2か月ごとだったり、最初の入金までに時間がかかったりするので、一定の貯蓄や家計管理が必要です。
収入が減ることに対して、不安を完全に拭うのは難しいかもしれませんが、事前の準備次第で乗り越えられるという実感があります。
資産形成していない…!という人は、まずは支出の最適化から始めると安心できると思います!


孤独感を感じることもある
育児休業中は、日中に社会と接点を持つ機会が極端に減ります。特に男性の場合、近所に同じように育休を取っているパパ友がいなかったり、児童館や支援センターに行ってもママばかりで肩身が狭かったり…。
こういった状況が続くと、社会から取り残されたような孤独感を覚えることもあります。これは女性の育休でも言えることですが、特に「男一人」の孤独は想像以上に堪えます。
それゆえに、僕はブログやSNSでの発信、同じ子育てをしている友人との情報交換などに努めているよ!
産休育休制度の相談先「ベンゾーさん」
育児休業の取得を検討し始めたとき、「制度の内容が複雑すぎる」「ネットで調べても曖昧な情報ばかり」「結局、自分は何をすればいいの?」と、情報の多さと分かりにくさに圧倒される方も多いと思います。
私自身もその一人でした。そんな中で出会って本当に助けられたのが、YouTubeで情報発信をしている「ベンゾーさん」でした。
Youtubeで育児休業について学べる
ベンゾーさんのYouTubeチャンネルでは、育児休業や出産手当金、給付金、社会保険の免除などについて、初心者にも分かりやすく解説されています。
- どんな手続きが必要か?
- 育休中の収入はどうなるのか?
- いつ何を申請すればよいのか?
こういったことを、分かりやすい動画で丁寧に説明してくれるので、「とにかく何から始めていいか分からない」という方にとって、非常に心強い味方です。
「もっと早くこの動画に出会っていれば…!」と本気で思いました。特に私のような“育休初心者パパ”にとっては、教科書のような存在です。
それでも分からない、不安な場合
YouTubeを見ても、どうしても不明点や個別のケースで悩む場面も出てきます。そんなときは、匿名で質問が投稿できる「マシュマロ」というサービスを活用するのがおすすめです。
ベンゾーさんは、YouTubeの生配信で寄せられた質問に答えてくれることがあり、気軽に質問できる場を用意してくれているのも魅力の一つです。
ただし、すぐに返事が来るとは限りませんし、個人情報が含まれるような内容をオープンな場で相談するのは難しいですよね。そういった場合には、有料相談という形で、より詳細なサポートを受けることも可能です。
自分の育休は“自分ごと”として調べよう
最後にお伝えしたいのは、「誰かが教えてくれるだろう」と受け身でいると、育休の制度や手続きは本当に分かりづらいということです。
ネットの情報だけで完結しようとせず、信頼できる情報発信者(今回で言えばベンゾーさん)を活用して、自分のケースに当てはめながら理解を深めていくことが大切です。
その過程で分からないことがあれば、マシュマロや有料相談を活用して、不安を一つずつ解消していく。これが、スムーズな育休取得への近道だと感じました。
さいごに
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
育児休業という制度は、「休み」ではなく「家族のための時間」であり、人生でも数少ない“家族の基盤を作る”大切な時期だと、私は実感しています。
- 男性が育休を取得する意味
- 収入や支出の不安への対処法
- 育休のメリット・デメリット
これらを包み隠さず書いたのは、これから育休を検討するパパ、そして「取ってほしいけど難しそう…」と悩むママの一助になればと思ったからです。
私もまだ育児のスタートラインに立ったばかりですが、育休を選んだことで得た経験や絆は、何ものにも代えがたい宝物です。
育児は一人ではできません。
パートナーと、家族と、そして社会の理解と支えがあって初めて成り立つものです。
もし、この記事があなたやあなたのご家族の“きっかけ”になるなら、これ以上うれしいことはありません。
これからも「育児」「お金」「夫婦のこと」について、リアルな視点で発信していきますので、よろしければぜひ他の記事もご覧ください!
オススメの関連記事
これで安心!戌の日の安産祈願レポ
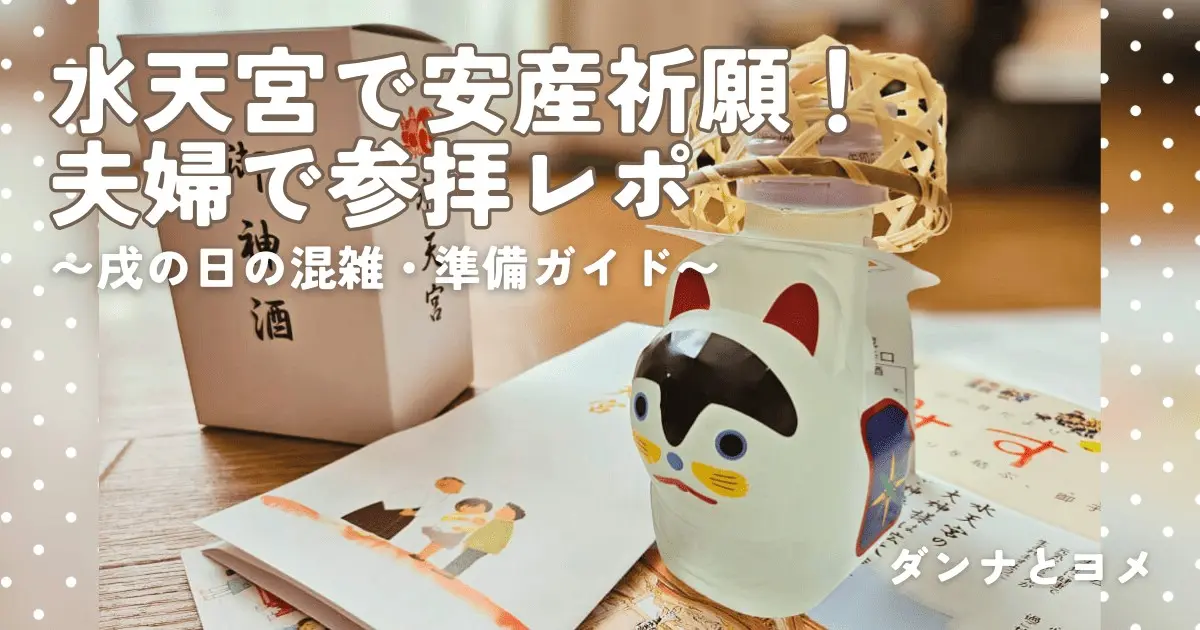
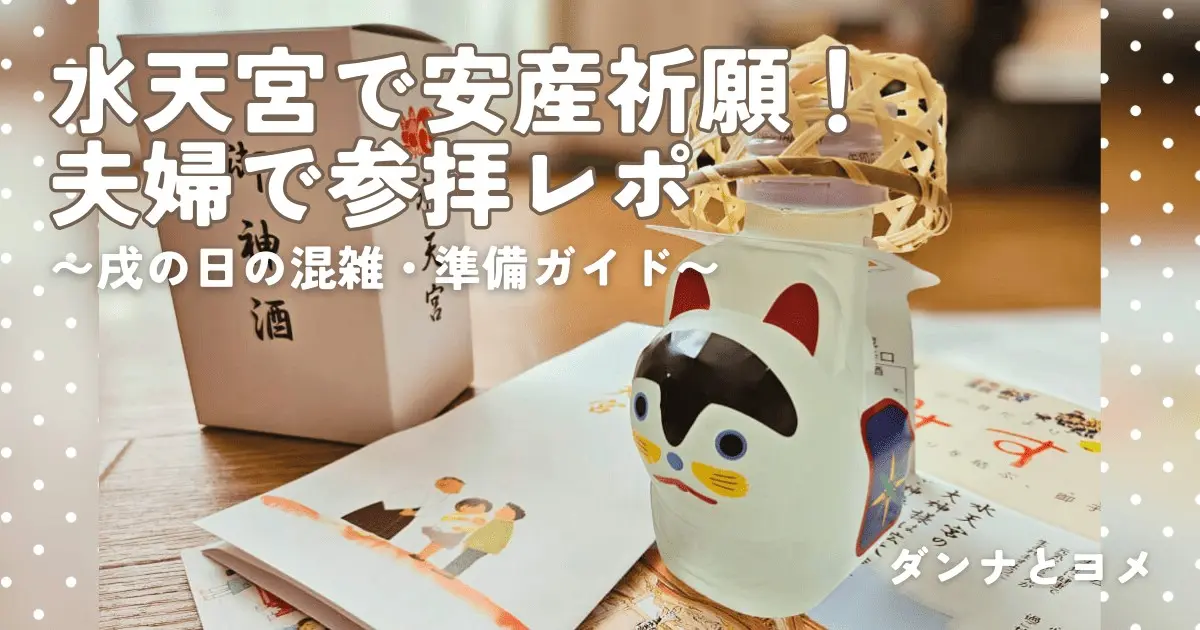
妊娠時期ごとの体験談
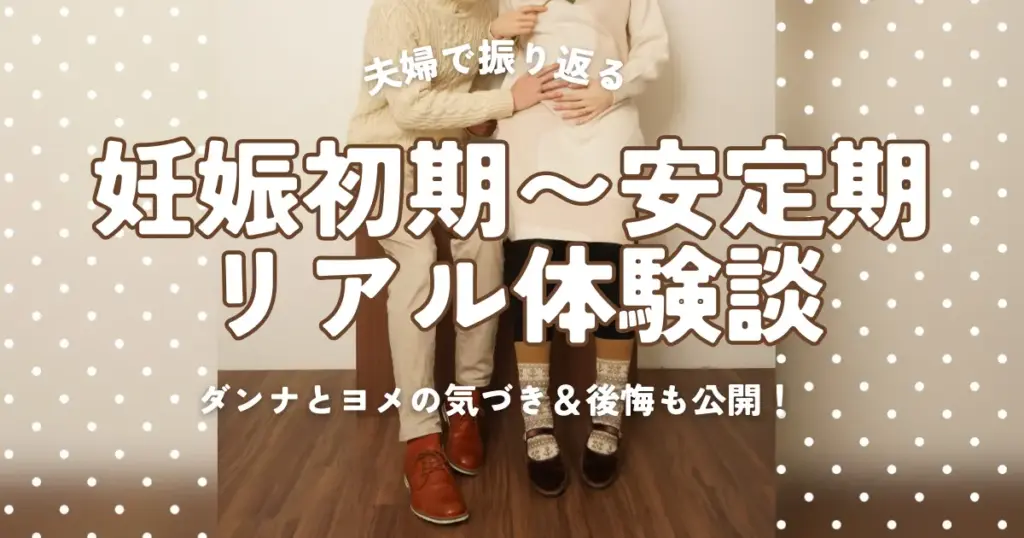
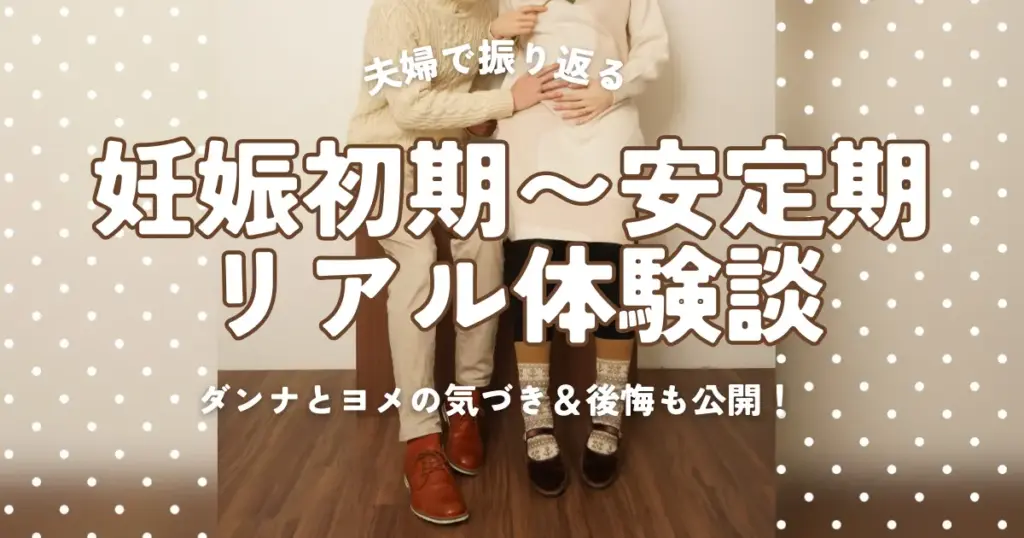
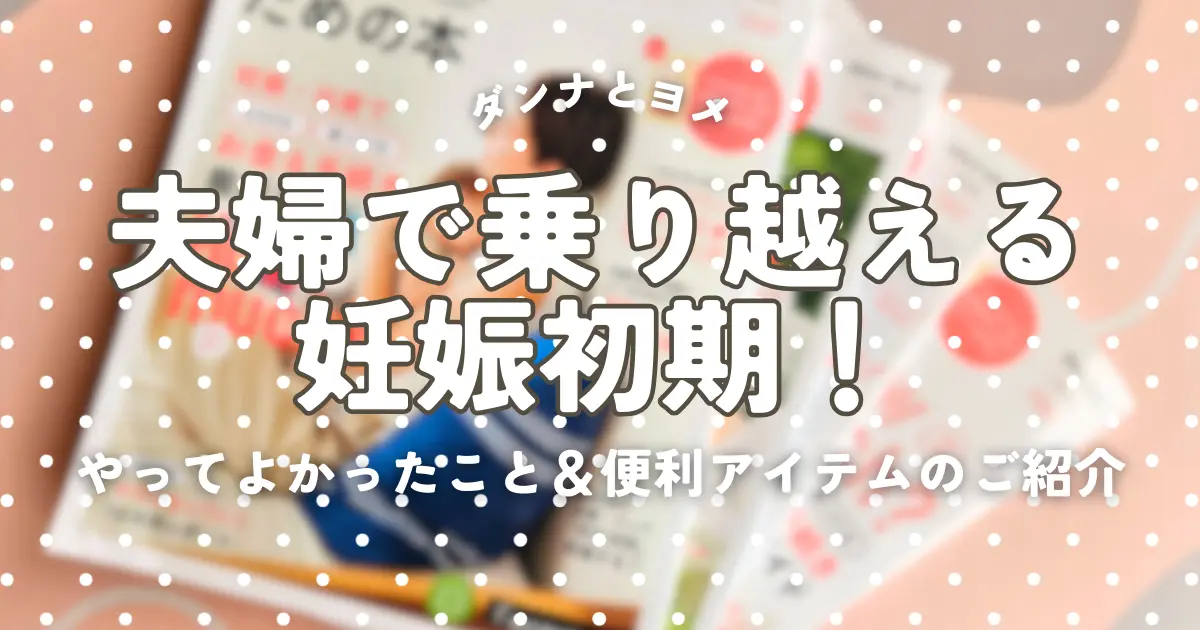
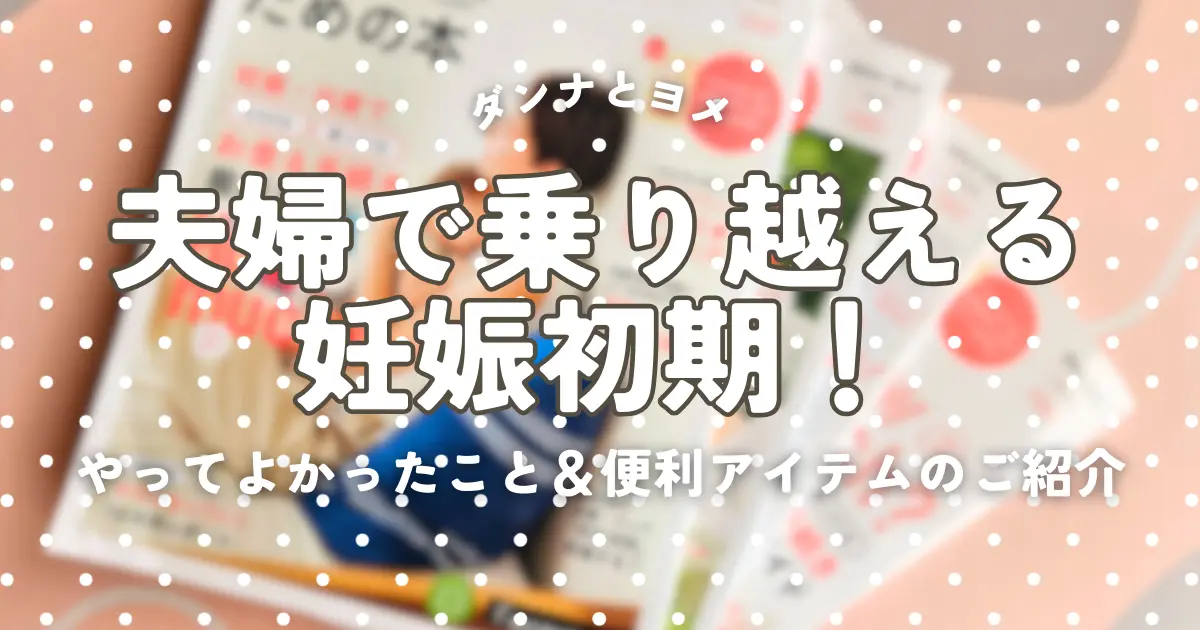


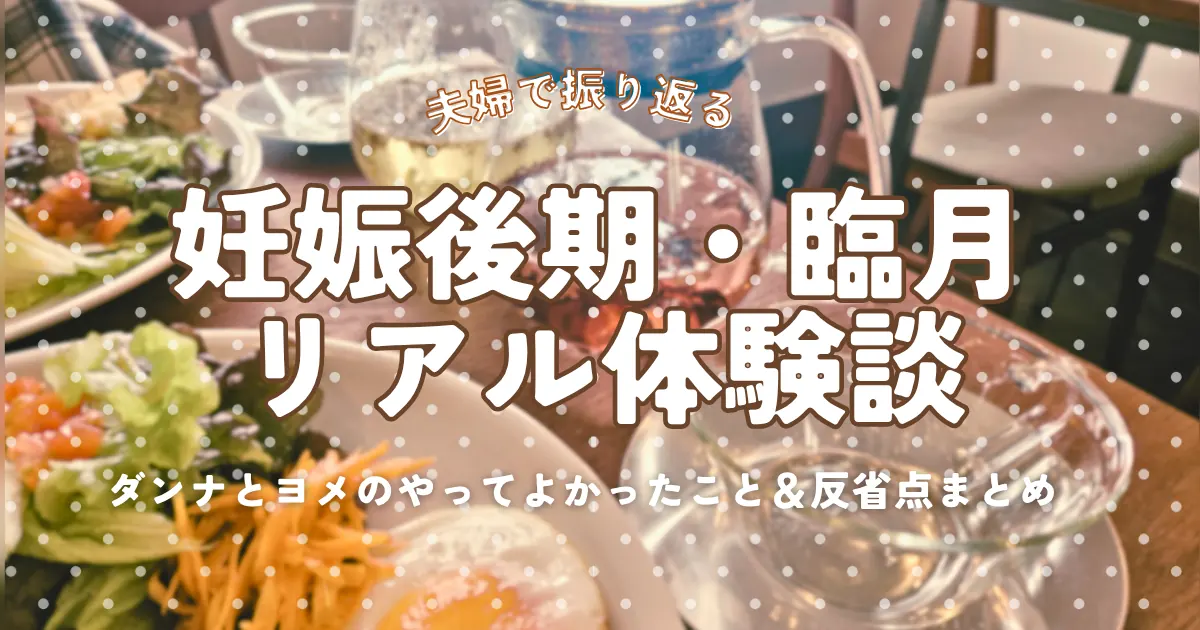
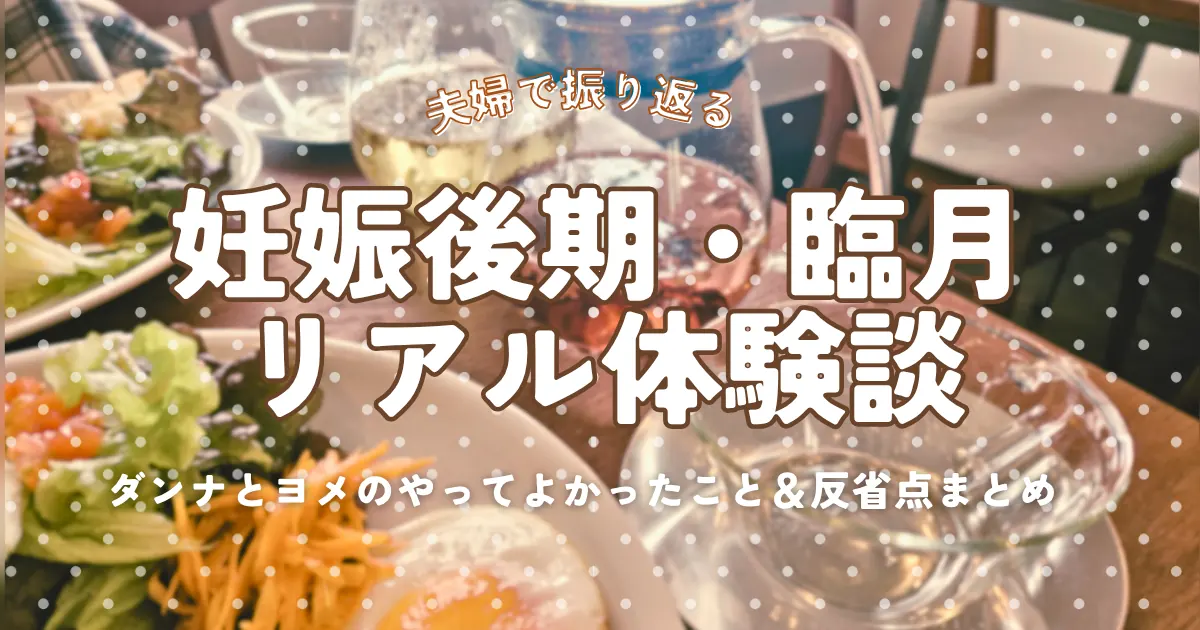
育児のリアルを綴った育児奮闘記
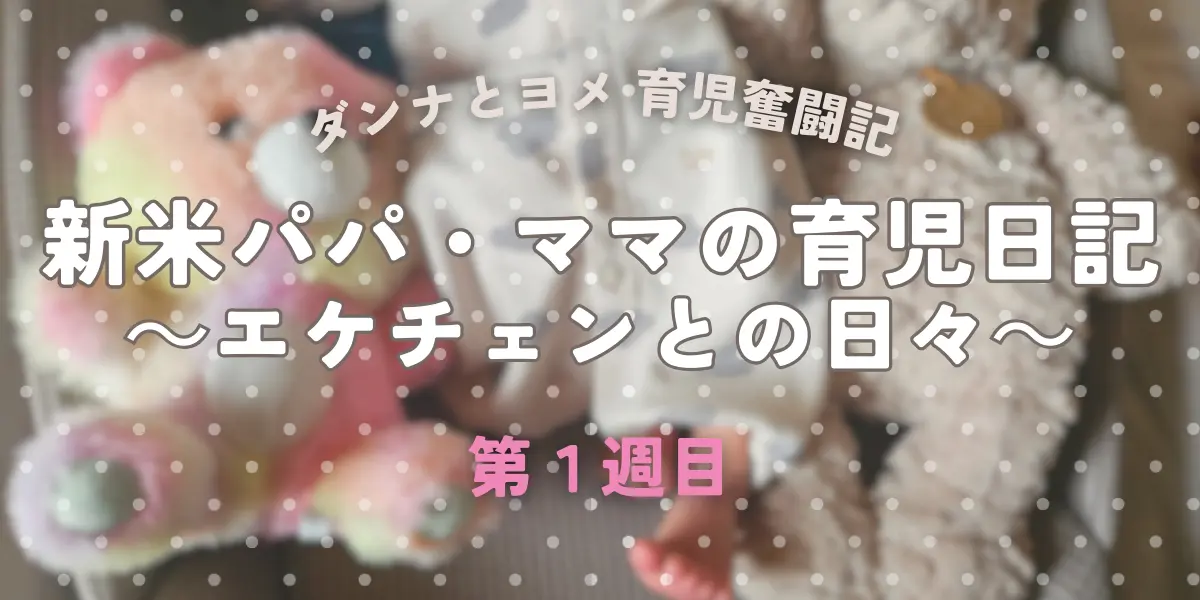
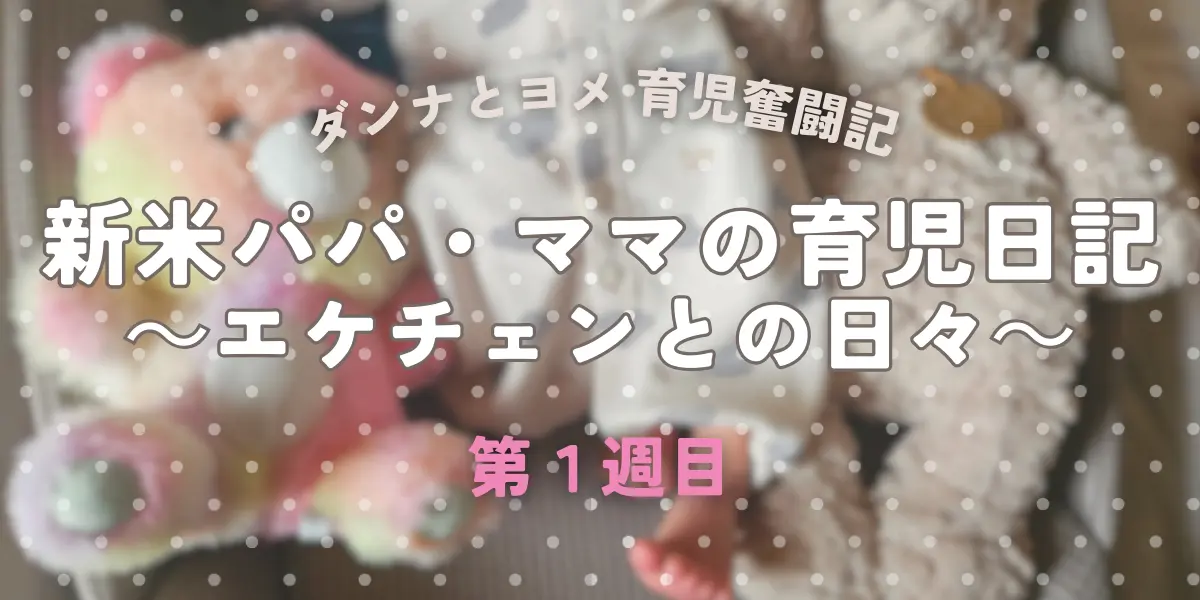
出産・育児準備に!
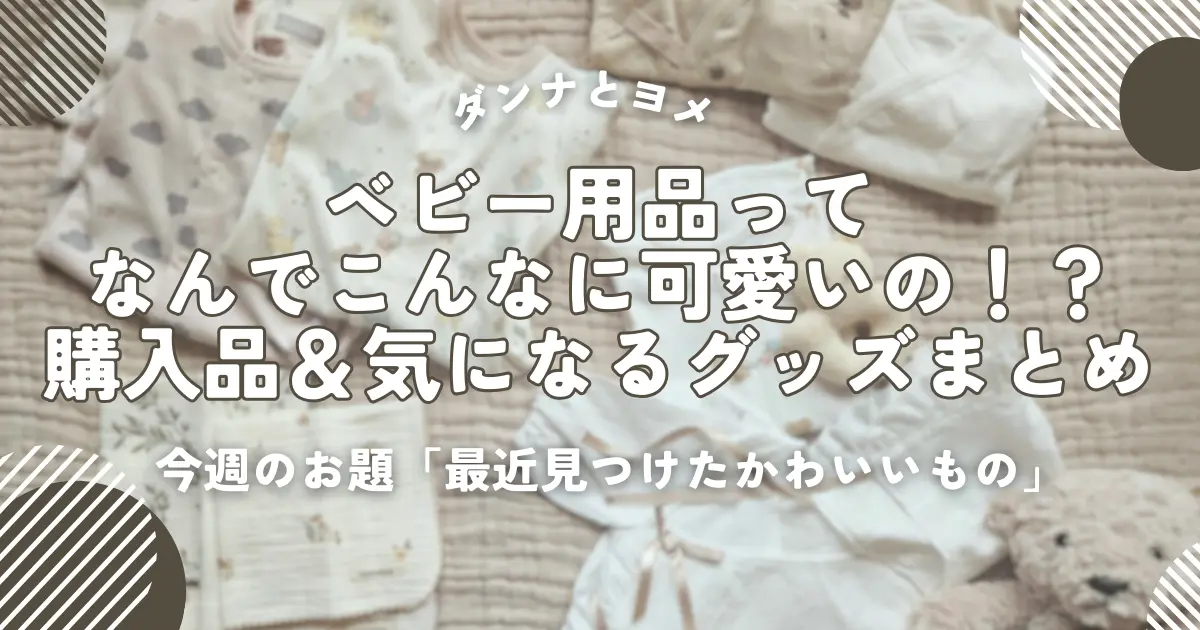
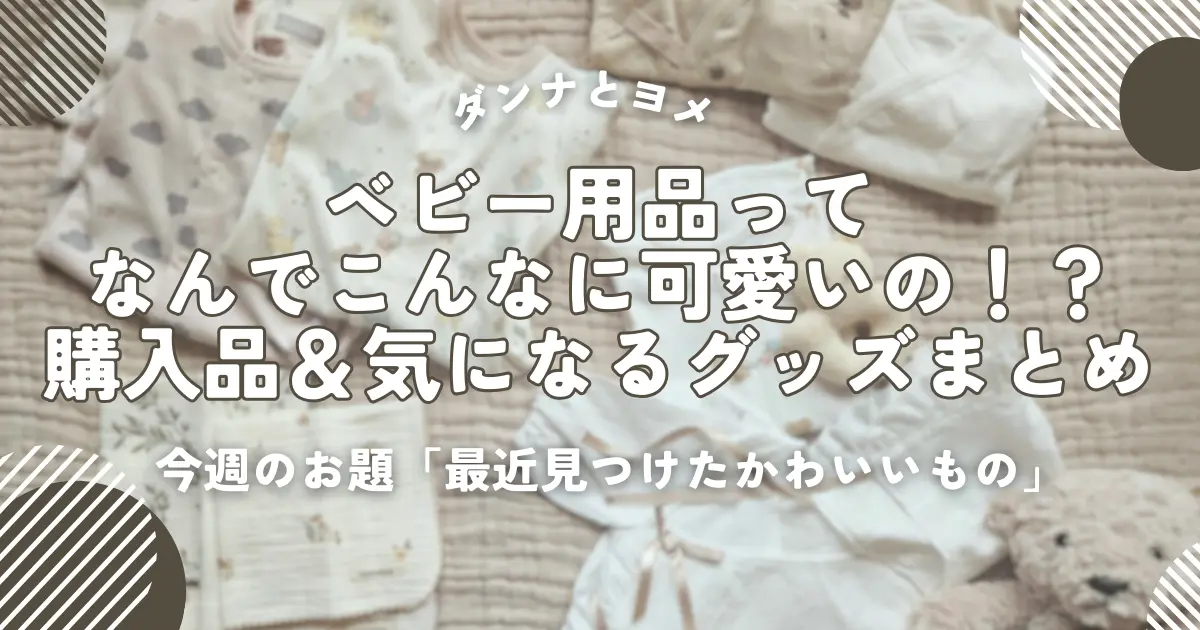
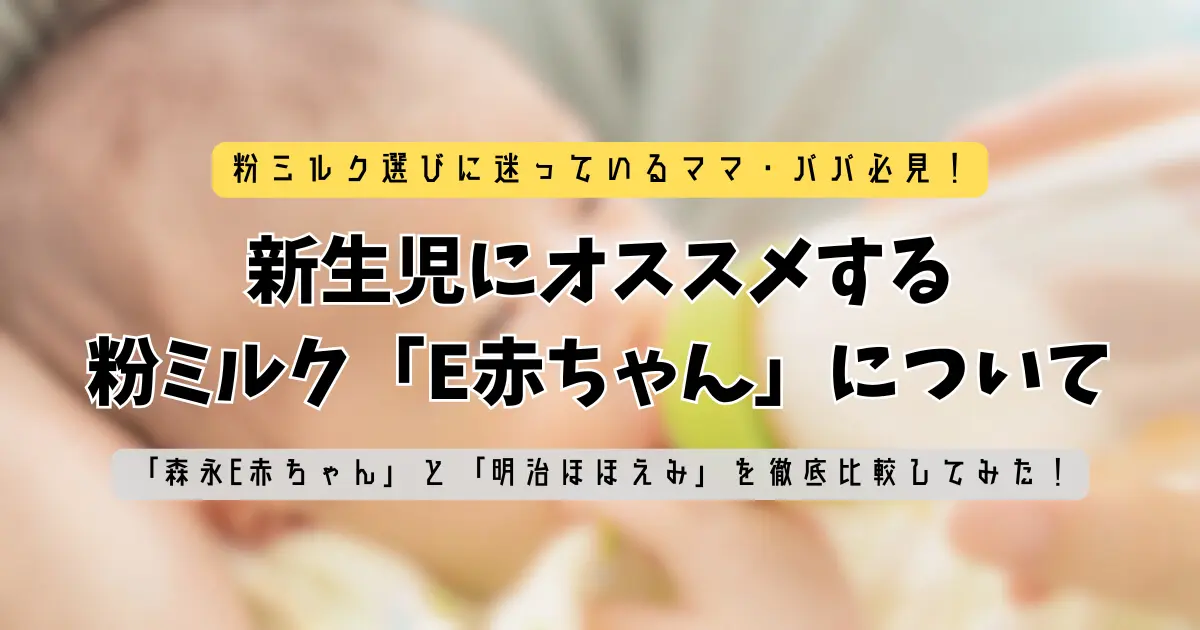
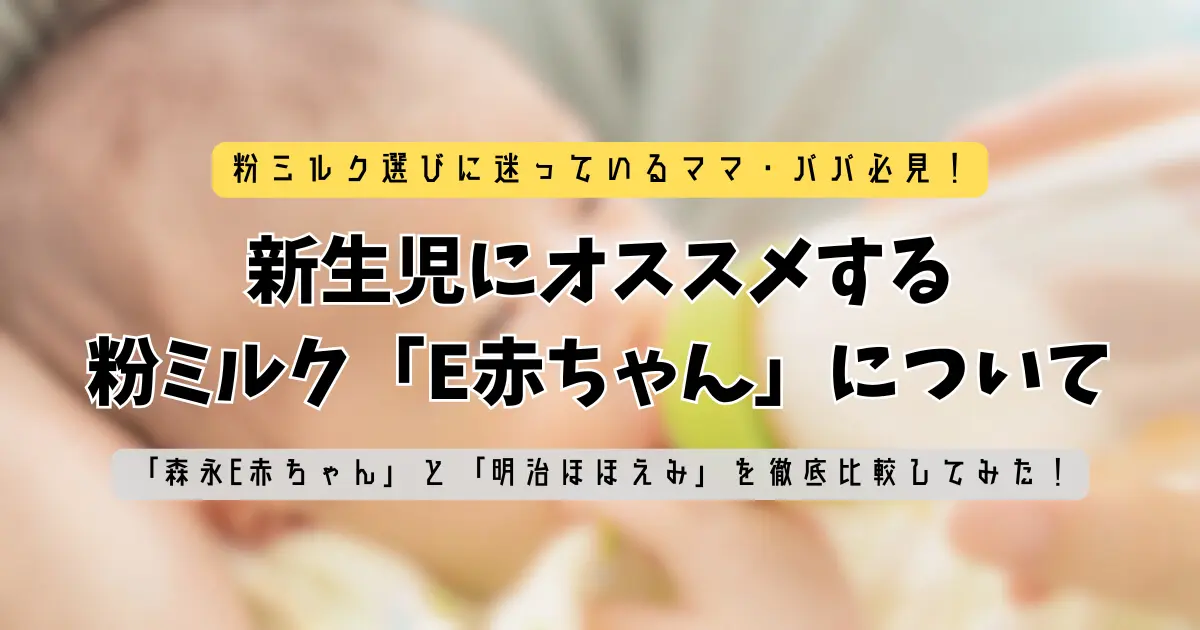
教育費用の不安を払しょくするために
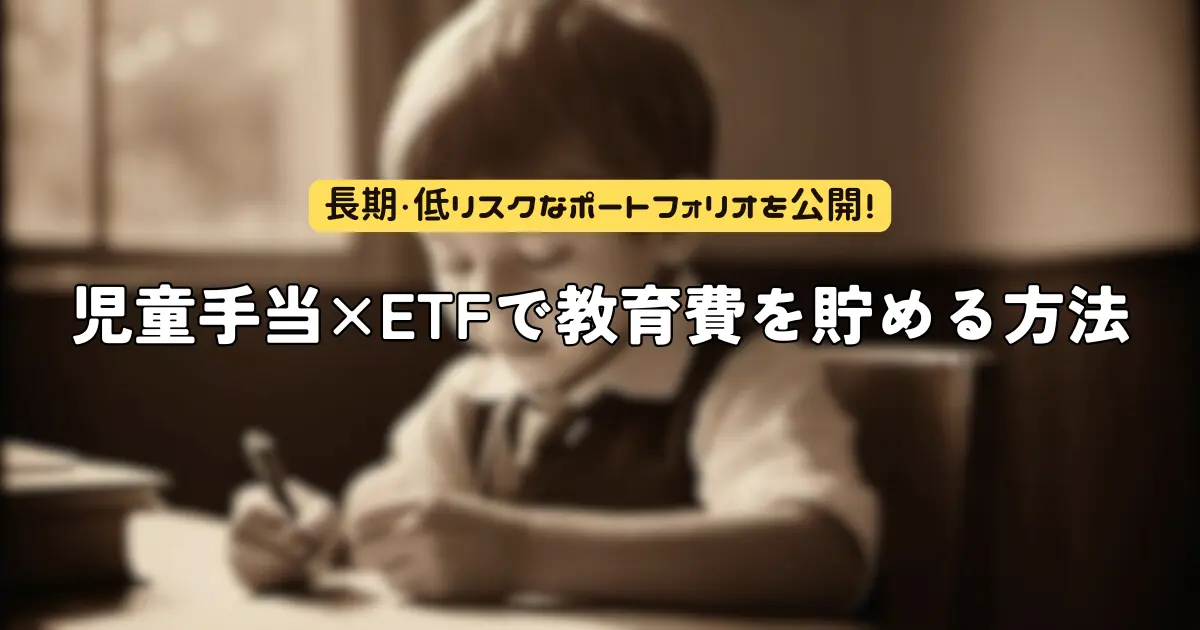
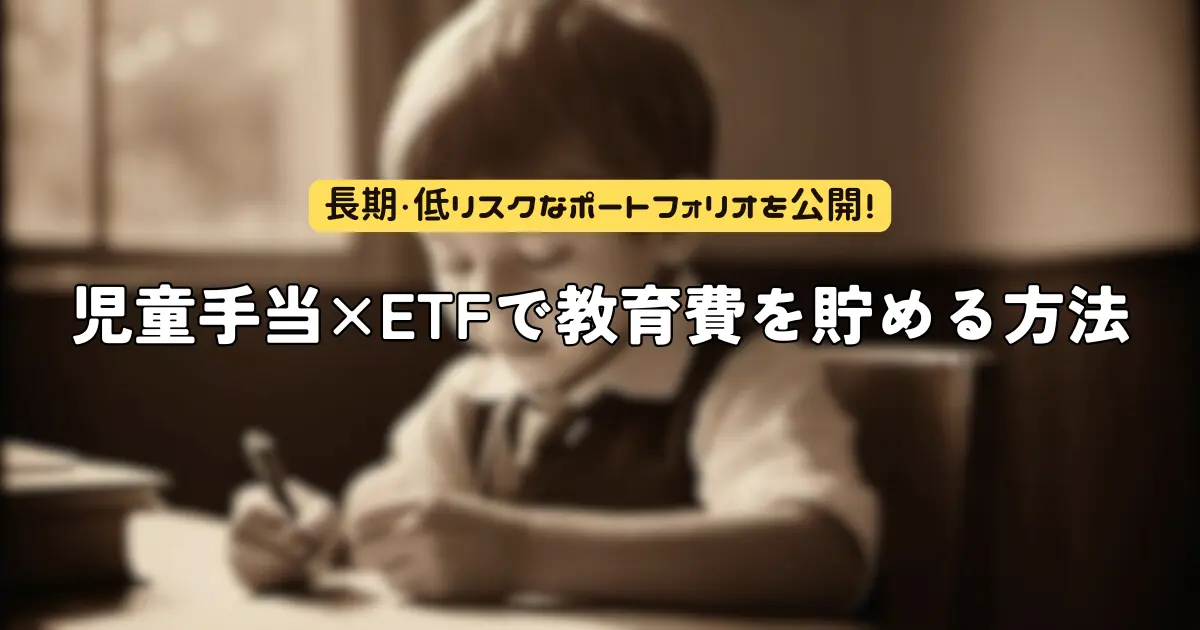
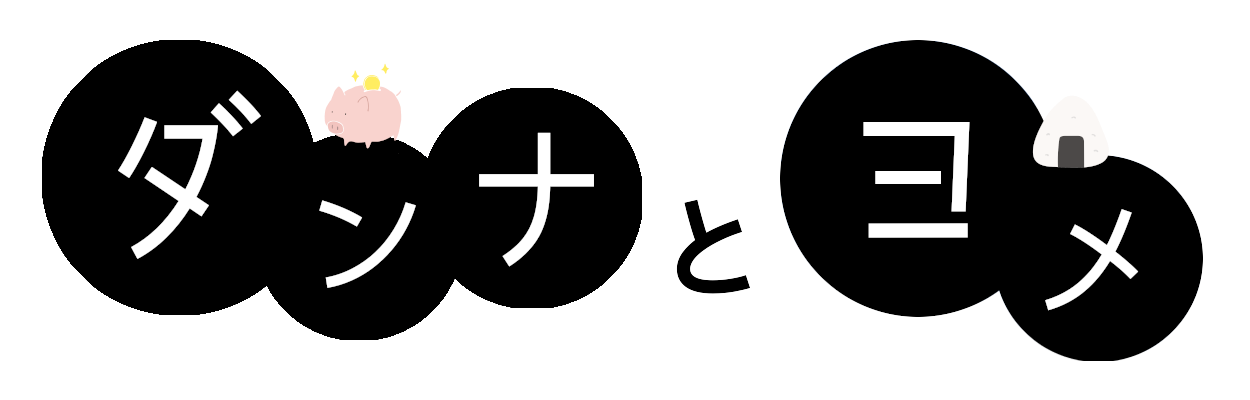

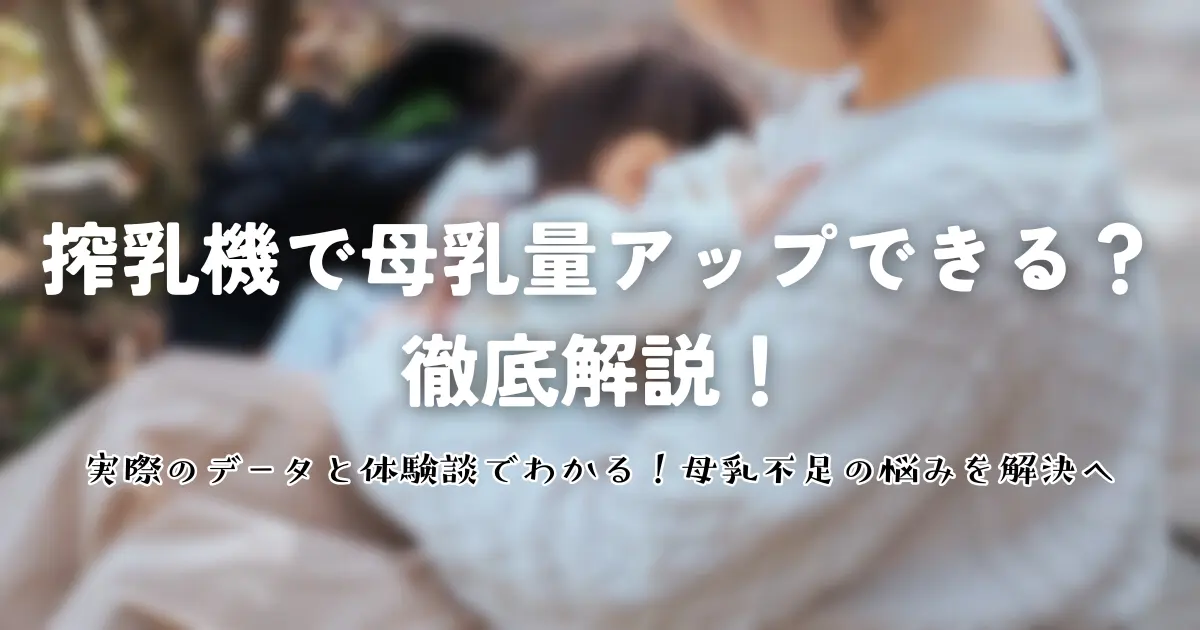
コメント