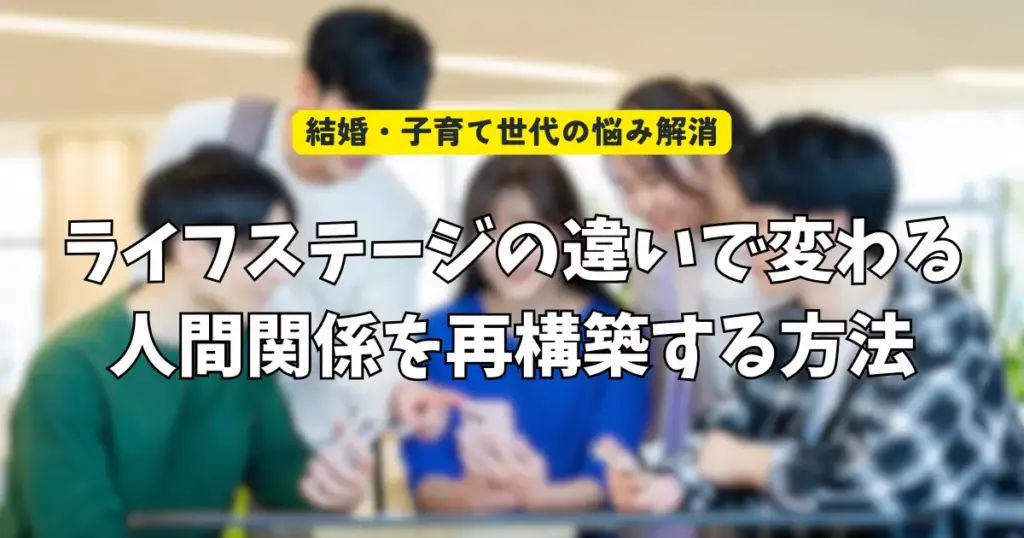
こんにちは、ダンナです。
結婚や子育てといったライフステージの変化によって、かつて親しかった友人や知人との関係が疎遠になったり、価値観にズレが生じるようになりました。僕が変わったのだろうと思いますが。
なぜ、こうした変化が起こるのか? どのようにすれば関係を維持し、より良い形に再構築できるのか?
本記事では、ダンナの面倒な性格が反映された理屈っぽい記事です。
社会学や心理学の知見を踏まえながら、その背景を探りつつ、具体的な接し方の指針や新しいコミュニティの活用法まで詳しく考えてみます。
きっと他の人も共通の悩みがあると思うんだ…。
ライフステージの違いがもたらす人間関係の変容とは
生活環境と価値観の変化
結婚や子育ては、個人の生活リズムや優先順位を劇的に変化させるライフイベントです。これまで自由に使えていた時間が制約されるだけでなく、社会的な役割も大きく変わります。
例えば、独身時代に共に遊んだ友人が子育てに追われる親になると、物理的な接触頻度は必然的に減少します。
また、子育て中心の生活では、自由な時間の使い方や優先すべき課題に対する価値観が異なってくるため、会話の内容や感覚にも乖離が生じやすくなります。
1日中、妻や子を置いて「遊びにいこう!」という気持ちにならなくなったのも大きいかも。
共感や理解の難しさ
こうした価値観や生活環境の差は、単に時間が合わないだけでなく、「相手の状況を理解しづらい」という心理的な壁も生みます。
子育て中の親は、独身の方は「自由で気楽そう」と言われると孤独感やストレスを感じやすいですし、一方で既婚者は「子ども中心の生活で自分がない」との言葉に傷つくこともあります。このように、相手のライフステージにまつわる言葉の受け止め方にズレが生じるため、無意識のうちに距離が広がってしまいます。
学術的に捉えるライフステージの違いと人間関係
ライフコース・アプローチ
ライフコース・アプローチは、人生を「役割の連続的な変化」として捉えます。就学、就労、結婚、出産などの転機は、個人の社会的ネットワークにも直接影響を及ぼします。例えば、結婚により交友範囲が家庭中心に変わり、旧友との接触頻度が減少するのはよくあることです。また、子育て期は親同士の新たなネットワーク形成を促す一方で、独身の友人との距離が広がりやすいとされます。
この理論では、人生の役割移行がネットワーク構造に与える変化を丁寧に分析し、ライフステージが違う人同士の相互理解が難しくなるメカニズムを説明しています。
ホモフィリー(Homophily)
「鳥は同じ羽を持つもの同士で群れる」という原理で説明されるホモフィリーは、年齢、性別、職業、家庭状況といった属性の類似性が人間関係の強さを左右するという社会学の基本的な考え方です。結婚や子育てなどのライフステージは属性の一部として作用し、同じライフステージの人同士がより強く結びつきやすい傾向があります。
このため、結婚して子育てをしている親同士は共感や情報共有がしやすく、関係が強固になる一方、属性が異なる独身者や子どもがいない夫婦との距離感は自然と開きやすくなるわけです。
ブラウ空間(Blau Space)
ブラウ空間は、社会的属性を多次元の座標軸で捉え、属性の「距離」が遠いほど交流機会が減少するとするモデルです。例えば年齢や収入、居住地などに加え、結婚や子育ての有無も属性として加えることで、ライフステージの違いが物理的な距離だけでなく心理的・社会的距離を生み出す構造が理解できます。
この視点からは、単なる疎遠ではなく、相互作用が起こりにくい「空間的な隔たり」として捉えられます。
コンボイ・モデル(Convoy Model of Social Relations)
コンボイ・モデルは、人生を船旅に例え、支援ネットワークを「護衛隊(コンボイ)」として捉えます。中心に近い関係ほど安定しており、周縁的な関係はライフイベントで入れ替わりやすいとされます。結婚や子育てによって生活が変わると、周縁的な関係は特に影響を受けやすく、疎遠化が進みやすいことが示唆されています。
ネットワークのターンオーバー研究
近年のビッグデータを活用した研究では、親密な友人関係の年間1~4%が入れ替わることが示されています。若年期よりも大人になるほど関係は安定しますが、結婚や子育てといった大きなライフステージの変化はターンオーバーを促進する主要因のひとつです。この定量的な知見は、感覚的な「疎遠化」を裏付ける科学的根拠といえます。
ライフステージの違いによるズレは「正常な現象」
小難しいことを話しましたが、意外とみんな悩んでいることが分かりました。だって研究されまくっているのだもの、日本国内外問わず共通の悩みなのかもしれません。むしろ、価値観や時間の使い方が変わるのは自然なことなようです。
重要なのは、その変化に「自分自身が、そして相手もどう適応するか」です。価値観の違いを否定せず尊重し合うこと、関係の形を変えても維持する努力が、人間関係を長く健康に保つ秘訣ということが分かります。
ライフステージの違いによる人間関係の乗り越え方
「役割の違い」を認めることから始める
まずは、異なるライフステージにある人の価値観や事情をジャッジせずに理解し、尊重することが大前提です。
たとえば、独身者が既婚者の「子ども中心の生活」に対して「自由がなくかわいそう」と評価せず、既婚者も独身者の「自由な時間」と「孤独や不安」の両面を想像して尊重することが関係の継続に不可欠です。
関係の更新に努める
過去と同じ関係を維持することを無理に目指すのではなく、形を変えた関係の維持を目指しましょう。
具体例としては、
- 以前は週末に飲みに行っていたが、今は年に一度の食事会で近況を語る
- 毎週電話をしていたが、子どもが寝た後の10分間のLINE通話に切り替える
- 毎日LINEでやりとりしていたが、誕生日や節目にメッセージを送る程度にする
- いつもは一緒に趣味の時間を過ごしていたが、ときどき参加する程度にする
このような「関係の形の変化」が、無理なく続けられる人間関係の鍵となります。
とはいえ、少しの(かなりの)疎外感が否めないのも事実ですが…。
関係の棚卸しも大切
すべての関係を無理に維持し続ける必要はありません。
疲弊感やストレスが続く関係は、距離を置くことも成熟した判断です。特に相手があなたのライフステージや価値観を否定し続ける場合や、心理的負担が一方的にかかっている場合は、穏やかにフェードアウトするのもひとつの選択肢です。
幸いなことに、僕の周りはそういった人が居ませんが…。
新しいコミュニティづくりのすすめ
なぜ新しいコミュニティが必要か?
ライフステージの変化に適応しやすい人間関係を作るためには、現在の自分と同じような状況や価値観を持つ人と出会うことが重要です。旧友は過去の共通点でつながっていることが多いですが、新しい仲間は「今の自分」を理解し共感してくれやすいというメリットがあります。
幼稚園や小学校の保護者同士の仲は、実は理にかなったものなのかもしれません。
僕の趣味の場合、親子で楽しめる機会を作っている方がいるため、子が成長したらお世話になりたいな~と思っています。今から楽しみ。
新しいコミュニティがもたらす効果
- 共感が得やすい:説明しなくても状況が理解されるため、精神的な負担が減る
- 自然体でいられる:過去のイメージや役割に縛られず、今の自分でいられる
- 安心感が生まれる:共通の価値観に基づくつながりは、心の安定につながる
具体的なコミュニティの探し方
- 地域の子育て支援センターや母親サークル
- オンラインの子育てフォーラムやSNSグループ
- 趣味や学びのサークル(ヨガ教室、英会話教室など)
- 地域のボランティア活動やイベント
自分の関心やライフスタイルに合ったコミュニティを探し、積極的に参加することで、新しい人間関係を築くきっかけになります。
まとめ
以上、理屈っぽいダンナが最近感じる、「友人とのズレ」について調べて、言語化した記事でした。
ライフステージの違いによる人間関係の変化は避けがたいものですが、その背景にはしっかりとした理論的根拠と心理的メカニズムがあります。重要なのは、価値観や時間の使い方の違いを理解し、尊重し合う姿勢を持つことです。
どちらが悪い!というわけではなく、仕方がないと割り切るのです。
また、関係の形を変えて維持する努力や、新しいコミュニティを積極的に探すことが、現代の多様なライフスタイルに対応した人間関係づくりに欠かせません。
人生の節目ごとに人間関係も変化しますが、その変化をポジティブに捉え、自分にとって心地よい関係を築いていくことが豊かな人生につながるのかな~と思います。
ヨメやエケチェンを大切に、友人も大切に、そして僕の人生も大切に生きていきたいと思う今日この頃なのでした。いつか皆でゆっくりと泊まりたいお宿の記事も読んでもらえると嬉しいです。


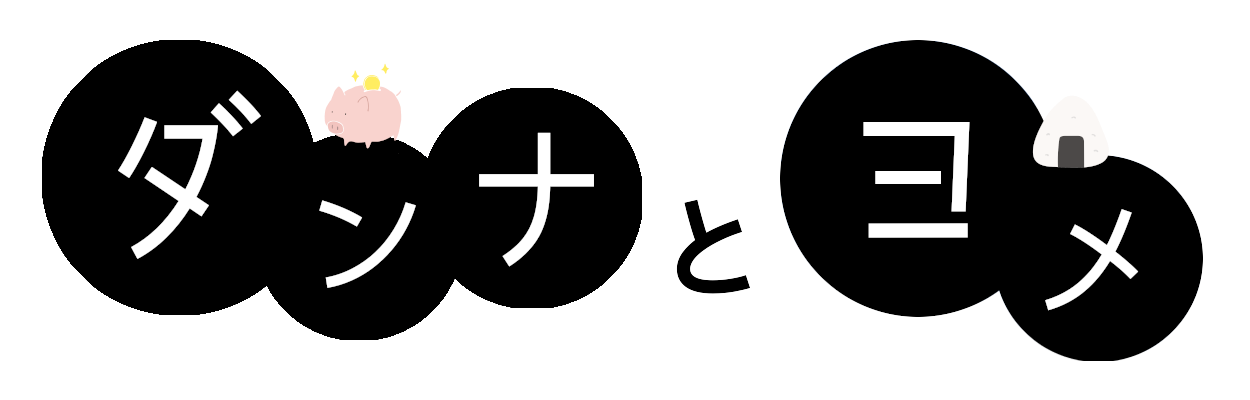

コメント